「ら抜き言葉」ってダメですか?
日本語のゆれ
ある語が変化する過程でその語形等について本来の形に対して桔抗する形が別に生じ、両者が並存する状態になったとき、これを言葉の「ゆれ」と言う。語形のゆれ(アタタカイ/アッタカイ、感ずる/感じるなど)のほかアクセントのゆれや表記のゆれもある。また、ある語に新しい意味・用法が生じ、本来のそれと並存する状態を「ゆれ」と言うことがある。 『文化庁HP』より
「ら抜き言葉」ってダメですか。
『日本人はよく「納豆食べれる?」とか「いつ来れる?」って言いますよね。これは、、、何ですか!?』
教室で学習者から必ず質問されるものの1つですね。本来あるべき「ら」が抜けているので「ら抜き言葉」と言われるものなのですが、皆さんは、この「ら抜き言葉」どう思いますか?私は、全然「ダメじゃない」派です。
「食べることができる」というとき、本来であれば「食べられる」というのが正しい言い方です。でも、会話では「食べれる」が一般的ですよね。同じもの・ことを表現する複数の言い方が一つの時代に共存している状態を「ゆれ」といいますが、「ら抜き言葉」はその象徴的なものの一つです。
「ら抜き言葉」に関しては、かなり前から「日本語の乱れだ」「文法的に正しくない」「いや、言葉は変化するものだから」などというような議論が活発にされてきました。
「ら抜き」が起こる理由
この「ら抜き言葉」、私たち日本語教師の間では「理由のある現象」とされています。学習者に「ら抜き言葉」で質問されたとき、私はこのように例文を挙げて説明しています。
この3文を見てください。
- ネズミがネコに食べられる。
- 社長が朝食を食べられる。
- 私はパクチーが食べられる。
この「~られる」という言い方は、可能表現と尊敬表現の両方で使われるから厄介ですよね〜。
ちなみに、1は受身、2は尊敬表現、3は可能表現です。
「見られる」、「食べられる」のように「ら」がある動詞(グループⅡ、またはru-verbs +来る)では、それが可能表現か、尊敬表現かの区別がつかないので、その区別をつけるために可能のとき「ら」の脱落が起きています。
もちろん、助詞を見たり、前後の文を読んだりすれば、その表現が1,2,3のどれに当てはまるのかすぐわかるとは思いますが・・・
「そのシャツ、着れますか?」「何時に来れる?」と言われたら、あー可能だなとすぐわかります。意味の曖昧さがなくなりますね。合理的だと思いませんか。
これって日本語を勉強する外国人にとってはどうなのでしょう。「食べれる」は「ら」がないから可能表現ということで、分かりやすくなるものなんですかね。いや、新しいことがさらに増えるのは嫌かな・・・ただ、こなれた感じには聞こえますね。まずは聞いてわかることが大事なのかもしれませんね。
さいごに
文化庁も「調査によると『見れた』や『出れる?』などの使用割合が本来の表現を上回ったが、逆転したのは『ら抜き』にすることで意味が正確に伝わる可能性が高い言葉ばかり。例えば『見られた』だと受け身の表現にも聞こえる。らを抜くと意図が伝わりやすいので、多くなっているのかもしれない」としています。
言葉のゆれ(乱れ)は、ときに言語を豊かに使いやすくしていく側面もあるようです。一律に否定せずに受け入れていってもいいのではないでしょうか。
あ、でも最後に大事な注意点を1つ!「ら抜き言葉」が使われるのは会話の場面だけです。会話でも丁寧さが求められるビジネスの場面、文章を書く場合は「ら抜き言葉」に違和感をもつ人が少なくありません。きちんとした文を書く場面では特に注意したほうがいいかもしれませんね。うーん、やっぱりどっちも必要みたいですね。
update 04/07/2023


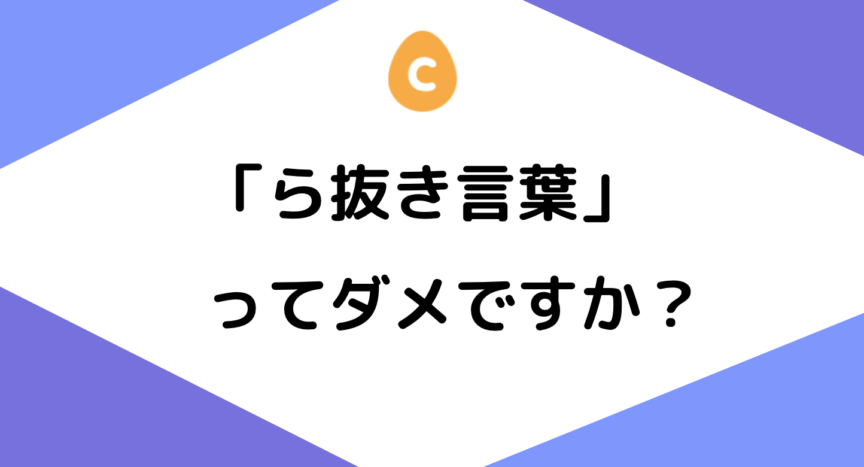
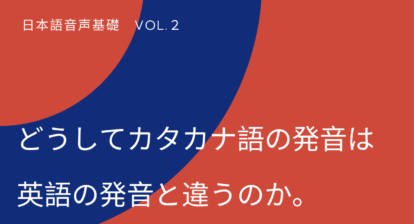
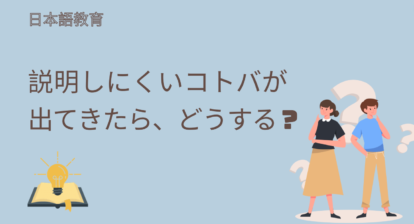

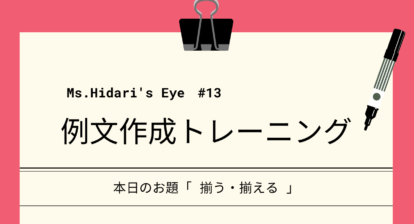
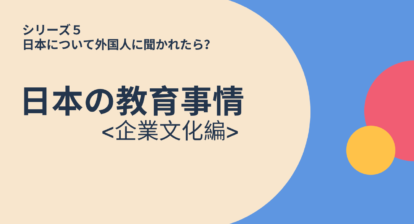

Customer Reviews
Thanks for submitting your comment!