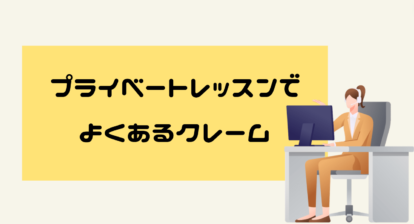Contents
“化石化教師”なんて言わせない!日本語教師が成長し続けるための習慣
「私はもう学ぶ必要がない」
もうずいぶん前の話になりますが、ある分野の先輩の仕事を見せていただく機会がありました。実はその当時、私は自分の仕事のやり方にあまり自信が持てなくて、仲介者を通してその先輩の仕事ぶりを見学させていただけるようお願いしていたのでした。
実際に拝見すると、その方の確立された仕事のやり方が随所にみられ、勉強になりました。私はその先輩に、仕事の考え方や今後の見通しなどをお聞きしたのですが、このようにおっしゃいました。
「私にはもう学ぶものは何もない。あなたも他人の仕事を見学するなんて殊勝よね」と。
…ええーっ!私なんて、毎回自分の仕事に対して反省しかないんだけど…!まだまだ勉強しないといけないことが山積みなんですけど!…と、考え方の違いにビックリ。そして、少しガッカリしてしまったのでした。
「化石化教師」にならないために
さて、日本語教育業界でも「教師の自己成長」という言葉をよく聞きますよね。
素朴な疑問なのですが、どうして日本語教師は成長しなければいけないのでしょうか?
成長しない教師 or 成長しようとしない教師はダメな教師なのでしょうか?
- 長年教えてきた経験があるから大丈夫!
- 今、特に大きな問題はないから成長なんて言われても…
- 日々授業の準備に追われているのに、「成長」とか「自己点検」とか「振り返り」とかウルサイ!
このように思う人がいても別におかしなことではないでしょう。
ただ、学生が日本語を習得しようと努力しているのに、教師が成長の努力をしないというのは言葉に重みが感じられません。
私が学生だったら、先生も何かしら勉強して努力している人の方がいいです。
また、成長がないということは、改善のための創意工夫をしていないということでしょうから、授業がただの流れ作業になり、仕事が単なる生活の糧を得る手段になっている可能性があります。これでは仕事の面白さや、やりがいは感じにくいかもしれませんね。
最近知ったのですが、CLL理論(Community Language Learning. カウンセリング理論を採用した外国語教授法)に基づく教師の成長仮説というのがあるそうで、それによると、ある程度レッスンに慣れてくると「一人前と認められてはいるが、それ以上の成長を望まない教師」に陥ってしまうことがあるのだとか。そのような教師を「化石化教師」というらしいです…。
化石化教師となって成長が止まらないように、「これでいいのかな?」「もっと良くならないか?」と、内省して振り返る姿勢が問われそうです
どうやって自己点検するか
ここからは、化石化教師とならないための自己点検の方法をご紹介していきます。
・ルーティンを作る(帰宅電車内反省)
これは多くの方が実践している方法で、特に「帰宅電車内反省」をしている方が多いようです。その名の通り、帰宅途中に今日のレッスンを振り返るというものです。帰宅中の電車でなんとなーくスマホを見て時間をつぶすのはもったいない。その時間を内省に使うことをルーティン化します。毎日のことなので、「良かった点1つ、改善点2つ」のように点検するポイントを絞った方が負担がなく習慣化しやすいでしょう。
・チェックリストで自己評価する
これも自己点検を習慣化するための方法です。「いつも同じ視点から自己点検してしまう」「ダメ出しばかりをしてしまう」という方におすすめです。
・授業記録をとる
授業でどんなことをやったのか記入するのは、すでに多くの方が実践していると思います。この授業記録に自分が工夫した点や、次回への改善点を追記していくというものです。
・学習者から評価を受ける
これができれば一番いいかもしれませんね!アンケートや直接聞くといった方法があります。
・他の先生からフィードバックを受ける
私が個人的に一番おすすめする方法です。自分一人では100年かかっても気づけないことに気づけるチャンスです。
・他の先生の授業を見学する
同じ文型なのにこうやって教えているのか!こういうツールもあるのね!と新たな視点が得られます。なお、Cotoオンラインでは互助会のしくみがあり、有志の教師同士がお互いのレッスンを見て学び合っています。
詳しくはコチラの記事(オンライン日本語教師は「孤独」なのか?【Cotoの取り組み】)でご紹介しています。
・自分のレッスンを録画して見る
自分のレッスンを見るのはなかなか恥ずかしいものです。客観的に自分を見ると、変な口癖があったり、思っていたより話し過ぎていたりと、嫌なところばかりが目立ち、私は見るのがツライです。。でも、見るたびに気づきがあります。
・勉強会に参加する
自分の課題に合った勉強会に参加することで、新たな知識や視点が得られるだけでなく、参加者同士の交流が深まるのも勉強会の魅力ですよね!
その他の自己点検の方法としては、自分も外国語を勉強する、視野を広げるためにいろいろなことにアンテナを立てる、異業種の人と交流する、などがあると思います。
全部やろう!とか、完璧にやろう!と思わず、肩の力を抜いてできるところから取り組んでいけたらいいですよね。
ポイントは「言語化」と「他者視点」
自己点検や振り返りには、先ほどご紹介したもの以外にもいろいろな方法があります。ただ、要は「言語化」と「他者視点」の2つがポイントであると考えます。
頭の中にあるフワっとした感覚を言葉にし、具体化・見える化することが「言語化」です。この言語化の過程で、良かった点や改善点の解像度が上がると考えられます。実は、私もこのコトハジメの執筆に携わることで、自分の課題を客観視する機会をいただいております。
そして、「他者視点を入れる」こと。他の先生からフィードバックを受けたり、学生からアンケートをもらったりすると、時には心にグサっとくることもあるかもしれません。ただ、自分から見える範囲には必ず「死角」があるものです。裸の王様にならないためにも、他者視点を入れる痛みは、必要な痛みであると思います。
なお、フィードバックの受け止め方については、コチラの記事に記載しています。
日本語教師のメンタルヘルス:学生からのフィードバックの受け止め方
成長に疲れたら…
ここまで教師の自己成長について述べてきましたが、自己成長の究極の目的は、教師本人&学生の幸せのためであると私は考えます。
「教師が成長する方が、より学生のためになるし、教師本人もハッピーになれる。だから自己点検する」というシンプルな原理を忘れると、苦しくなってしまうかもしれませんね。
教師を苦しめる思考に、「成長しなければいけない(完璧主義)」「成長するべき(べき論)」といった思い込みがあります。もし成長することに疲れたらこの思考に陥っていないか、ちょっと振り返ってみましょう。
日本語教師が病まないために:日本語教師のメンタルヘルスを考える
また、ハードルを低くするのもいいですね。「今日はいつもよりちょっとだけ笑顔を増やそう」「あの学生さん苦手だけど、1つでいいから褒めてみよう」といった小さな試みで十分だと思います。この小さな変化、小さな成長も繰り返していけば、塵も積もれば山となるで、最終的に大きな変化となるはずです。
私は、新入社員のころに上司に言われたことがあります。「毎月の収入の1割を自分の成長のために使いなさい。今はわからないかもしれないけど、10年経ち、20年経ち…と時間が長くなればなるほど、続けてきた人とやらなかった人とでは差が大きくなっていくから。」
私はとっても素直な人間なので(笑)、今でもこの上司の教えを守っています。たいした能力もない凡人ではありますが、この教えを守ることで出会えた仲間・知識・チャンス・仕事があります。あの上司の言葉に今は心から感謝しています。