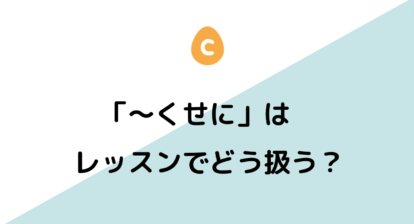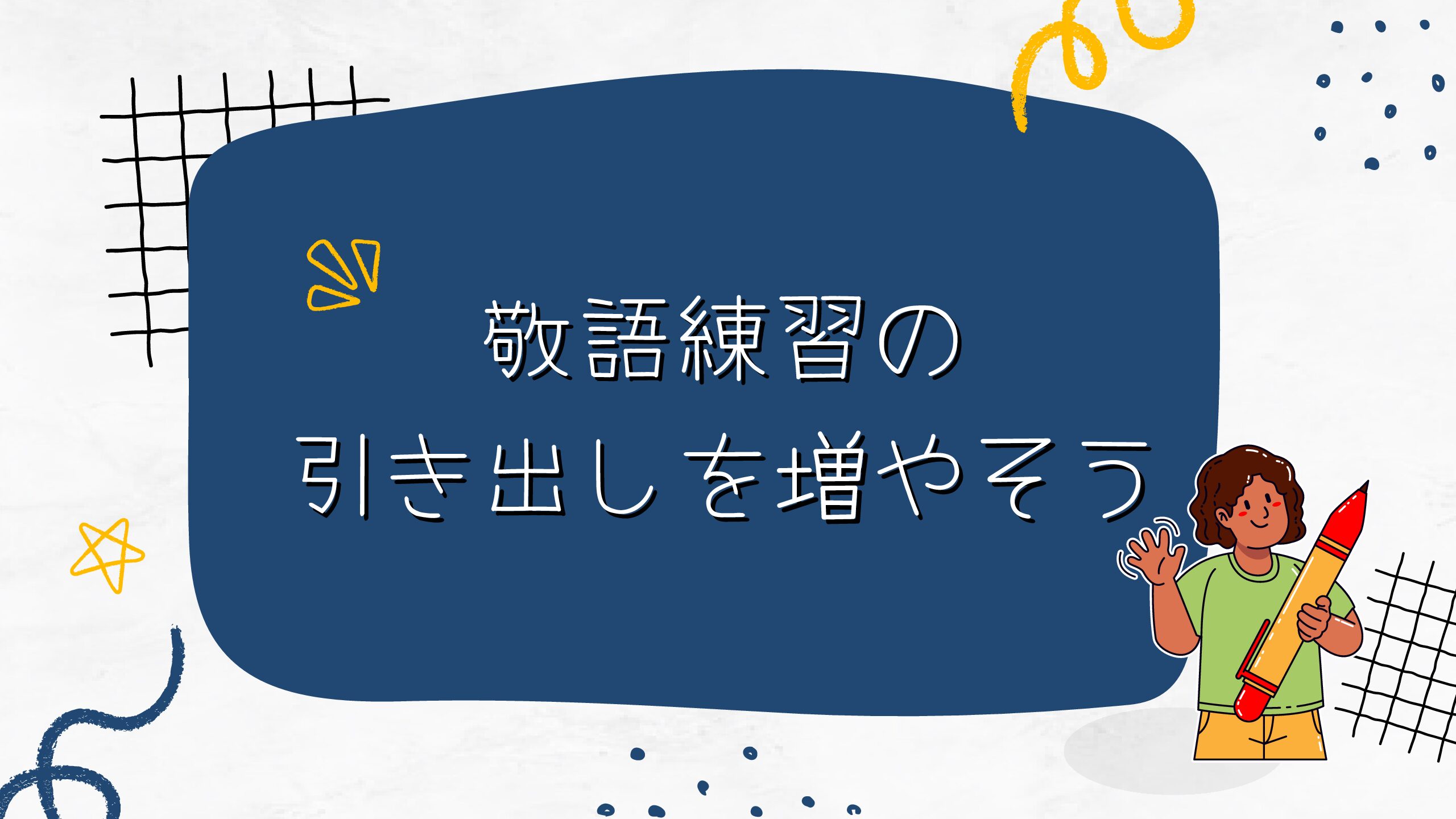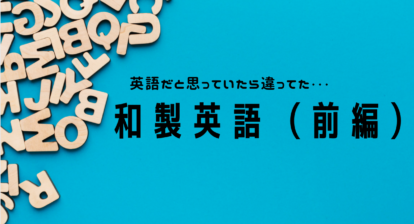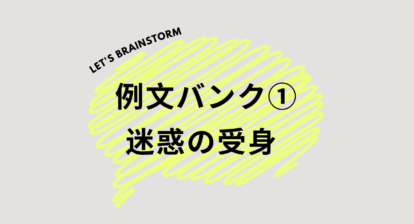実は難易度が高い:初級文法「~たり、~たり」
はじめに
「たり、たり」は日本語では日常的に使用頻度の高い文型の一つです。
例)
①休みの日は、たいていジムに行ったり、散歩したり、のんびりすごすことが多い。
②
A:日本のお正月って何するの?
B:おせちを食べたり、近くの神社に初詣に行ったり、テレビをみたり…かなあ。
③今日は子どもの行事で学校とうちを行ったり来たり忙しかった。
上記の例文にもあるように、「たり、たり」の機能は、ある時間や限定的な状況・イベントで行う動作や行動から典型的なものを列挙するのが一つ。また、そこから派生して、やることの多さからくるせわしなさを表現するときなどにももうってつけの文型で、学習者がこれを理解し、使いこなすと、会話はより生き生きと自然に聞こえます。
が、学習者にとって「たり、たり」は、理解しにくい文型のひとつでもあります。また、(今までの私の経験則ですが)理解したとて自然に使いこなすのが難しい文法のようにも感じます。今回は、そういった学習者が難しく感じるポイントを探ることで、講師にとって、より適切な導入文はどれか、導入時の注意点は何かを探りたいと思っています。
難しいところ(学習者の混乱の原因)
学習者のスムーズな理解を妨げる障壁としては以下の3つが考えられると思います。
1)既習文型「~て、~て」との違いがわからない。
「げんき」では6課の「て形」の活用の導入と同時に、「て形」を使用した文型の一つとして「て形接続」が導入されます。この文型との違いがわからず混乱する学生は少なくないです。混乱の原因は母語干渉が多いのかなと思っています。というのも、例えば英語でいうと、どちらも「AND」でまかなえてしまうからです。
例)
今日はジムに行って、散歩するつもりだ。
Today I’m going to the gym and then plan to take a walk.
休みの日はジムに行ったり、散歩したりする。
On my days off, I go to the gym and take a walk.
日本語では、「~て、~て」と「~たり、~たり」には大きな違いがあります。
それは「~て、~て」は時間軸に沿って行う行動、「~たり、~たり」は時間軸を無視して、ある時間の中の行動をただ列挙するという違いです。これは、学生からもよく聞かれる質問なので学生向けには、以下のようにするとよいでしょう。
「~て、~て」
私は毎朝6時に起きて、シャワーをあびて、7時半に会社に行きます。
※具体的な時間を上げ、時間軸にそって、順番にその行動を行うことを明らかにします。
「~たり、~たり」
私は朝からジョギングをしたり、庭仕事をしたり、podcastを聞いたりします。
※時間軸は関係なく、朝の時間にすることを列挙します。行動の前後や重要性なども問わずフラット、ただの例示です。活動内容ですが、他のあまたなこと、シャワーをあびる、あさごはんをつくる、コーヒーをのむ、などたくさん挙げて、その中からいくつかピックアップして言っているということを明らかにしておくのが大事です。
また、英語がわかる人には各文型の機能を理解する英語語彙として、「~て、~て」timeline、「~たり、~たり」listingという言葉を添えると、理解しやすい場合があります。必ず聞かれる既習文型との違いについて、以上のように適切に回答できれば学習者にとっての理解文型から使用文型にまで引き上げることができます。
2)「た形」を「過去形」と理解することで混乱する
「た形」は活用形の一つであり、「た形」=「過去形」ではありません。もちろん、casual speech styleや書き言葉において「過去」という時制を反映するものではあります。が、それが「た形」の機能の全てではありません。
「た形」は、ある文型を構成する文法要素の一つとして用いられることが中級以上ではとくに増えてきます。初級のこの段階で「た形」=「過去形」という考え方を払しょくしておく必要があります。(ちなみに初級でも「~たほうがいい」「~たらどうですか」「~たことがある」など必ずしも時制とは関係のない文型が出てきますので、折に触れてこれらの文型内の「た形」には時制はないと言い続けたほうがいいでしょう)
「~たり、~たり」は、文法の構成要素に分解すると、ta-form+り、ta-form+り、であり、「列挙・例示」の機能を持つ文型(structure)であること。その文型内で、活用形の「た形」は文型構成要素として使われているに過ぎないということを、まずは理解させる必要があります。
また、そうなると時制が気になる(過去のイベントの動作の列挙はどうする?)と思うので「~たり、~たり」の時制は必ず文末に現れることを早い時点で出すといいです。
例)
Q:昨日の晩、何をしましたか。
A:(昨日の晩)うちで宿題をしたり、テレビを見たりしました。
Q:今晩、何をしますか。
A:(今晩)うちで宿題をしたり、テレビを見たりします。
3)使用場面がわかりにくい
「~たり、~たり」の機能は「例示」であると言われても、学習者はすぐにはピンと来ません。母語を始めとするその人の持つ言語環境や背景によっては、その説明だけで使用場面を想定できる人は非常に少ないのです。このことをまずは教える側が知っておく必要があります。
なので、導入時に適切な場面と例文を考えることが学習者の理解を助けます。では、「例示」をすべき、したくなる、しなければならない場面はどんなときでしょうか。それは当たりまえですが、列挙するいとまがない、たくさんの例がありすべて全部挙げるのは(時間的にも知識などの能力的にも)困難だと感じるものがよいです。
たとえば一番いいのはイベントごとです。例えば、クリスマス、お正月、結婚式など。しかし、ここには罠があります。それは語彙の特殊さと難しさ。イベント系の語彙は、文化依存の語彙が多く、初級の学生には例文が理解しづらいことが多いです。例えば、日本のお正月を説明しようとすると「おせち」「初詣」「年賀状」などの語彙から説明しないといけません。他の国の文化的行事や宗教的行事も同じです。とうわけで、文化的イベントは、導入や練習にはあまり向かないことが多いです。
他に導入向きのイベントはないか。夏休み・冬休み・ゴールデンウィークなどの長めの休み、あるいは旅行など一般的かつ普遍的なイベントはどうでしょうか。会話の発信者にも聞き手にとっても理解がしやすいという意味の典型的なイベントで、語彙の難易度が低く、文化差が小さいジャンルであれば良さそうです。
また典型的な週末を説明するのもいいかと思います。週末にはおそらくみなさんはいろいろなことをするかと思うのですが、その中でも典型的な週末の行動について話してもらうのです。まずは講師が例を出すといいでしょう。
例)
先週末、ディズニーランドに行きました。子どもの誕生日でしたから。(→これは特別なケースであったことを伝える)
でも、たいてい週末は、うちでごろごろしたり、本を読んだり、散歩したりします。
まとめ
「たり、たり」は難しい文型か、と問われたら、学習者からは「はい」でしょう。基本文型としては使用頻度も高く、必須ですが、概念的難易度は中級寄りかと思われます。
理由は、以下4点。学習者が理解時に複数の認知プロセスに同時アクセスしなければならないからです。
(1)列挙の概念理解(網羅的でなくてよい)
(2)時間軸を外すという発想
(3)「た形」を中立的な形(「過去形」ではない)として捉えるメタ的理解
(4)「全部言わない」=例示 の文化的・語用的理解
これらが重なるため、初級後半で導入されるわりには、自然運用までに時間がかかる文型と言えるのではないでしょうか。