ティーチャートークとはなんぞや
最近、模擬授業などを見ることが時々あるのですが、そのときに気になるのが教師の発話。「その指示だときっとわからないだろうな〜」「あー、日本語で説明したらもっと混乱しちゃうのにな〜」なんてことがあります。
皆さん、ご自身が外国語を習った時のことを思い出してください。語彙や文型、スピードをコントロールせずに話されたら、「なにもわからん…あー無理」となってしまいませんか。一方で、自分がわかる言葉で、またわからないことをわかるように言ってくれたり、理解できるように繰り返してくれたりする講師に教えてもらうと、わかることが少しずつ増えてきたなんてこともあります。
教師の発話のわかりやすさは学習者の理解度に関わってきます。なので、私たち日本語教師は目の前の学習者にとって、わかりやすい話し方をする必要があります。学習者のレベルに合わせて、文型・語彙・スピードをコントロールしながら話します。これを「ティーチャートーク」と言います。
「自己モニター」なんてことばを日本語教師になるときに勉強しましたが、これは学習者だけでなく我々にも言えることです。客観的に自分を観察する一番の方法は録画・録音です。単調でつまらないと思ったレッスンは、誰が見たってつまらない。そのつまらない要因は色々考えられますが、まずはじめに自分自身の「ティーチャートーク」を振り返ってみると良いかもしれません。
以下の3つが「ティーチャートーク」振り返りポイントです。
1. 文型のコントロール
「まだ習っていない文型は使わない」で話すというのは鉄則です。未習文型で教師が説明やキュー出しをしたら、学習者は理解できません。それは音楽か雑音と同じです。また、一文の中にいくつもの文型が含まれているような複雑な文だったり長い文だったりすると、そこが気になって集中力も途切れてしまうので、気をつけたいです。
特に初級のレッスンでは「文型のコントロール」は大切です。いつどこで何を習っているかをしっかり把握しておく必要があります。導入の際はわかりやすい場面設定、指示は既習語彙を使用してシンプルに短く、導入文は既習語彙使用+1文の中に文型1つ!を心がけたいです。
おそらくテキストを何周か教えていないと全ての文型は頭に入りませんから、文型リスト(※)を準備しておくと良いでしょう。日本語教師になったばかりの方は自身の発話すべてに注意を払い、教案を作っておくと安心&安全です。
また中上級になると、学習者から「AとBの文型の違いはなんですか」なんて質問も出てきます。つい親切心で丁寧に深く説明したくなりますが、説明しようとするとつい未習語彙を使ってしまいます。でも学習者はたいていそれでよりわからなくなります。教師自身も混乱してしまい、身動きが取れなくなるなんてこともあります。こんなときこそ「例文をあげる」「言い換える」「短文/単文にする」などの方法でシンプルに!を心がけると良いかと思います。
2. 語彙のコントロール
文型のコントールと同様、語彙のコントロールもマストです。コントールしていないと、「え、なんだって?今のことば、何??」と、学習者の意識がわからない語彙に向かってしまい、意識が逸れてしまって本来伝えたいことが伝わらないなんてことがあります。
既習語彙が頭の中に入っていない場合はレッスン前に下記のような語彙リスト(※)を見て確認しておきましょう。文型の導入時はできるだけ易しい言葉を使ったほうがいいです。ただ、学習者の趣味や嗜好、仕事などを把握していて、この語彙で文型導入したら刺さるはず!というケースもまれにあります。そんなときは、事前のウォームアップなどで導入で使う語彙を学習者と確認をしておくといいですね。
機能と形がしっかり理解できていることを確認し、一通り基本練習がすんだら、段階的に語彙のレベルをあげていきます。私はその学習者が日本で生活する上で、または仕事をする上で必要そうな語彙はテキストに載っていないものでも媒介語をつかってサラッといれてしまう場合もあります。ただし、あくまでも学習者に余力がある場合のみです。知りたい気持ちは止められませんが、人の記憶のストレージもそれほど大きくないと思いますので、くれぐれも数は調整してくださいね。
(※参考資料:『げんき』文型&語彙リスト)
3. スピードのコントロール
ゆっくり話せば理解できるというわけではありません。話すスピードがゆっくり過ぎて、日本語らしくなくなるのも問題です。教室の外に出て、「先生の話はわかるけど、外で日本人と話すと全くわからない」では困ります。ゴールは日本人の会話がナチュラルスピードでわかること、私たちもこのゴールを意識したいです。
教師の発話のスピードは学習レベルに応じて徐々にアップさせていきましょう。こちらがテンポアップすれば、つられて学習者の発話スピードもアップします。またパターンプラクティスなどの時は、ある程度のスピード感があったほうが緊張感も集中力も増し、学習効果も上がるのでオススメです。
もちろん、その語彙や文型が初出だとか、聞き取れていない場合はゆっくり&はっきり話す必要があります。ただ、学習者が初級レベルだからといって、ずーっとゆっくり話す必要はまったくありません。耳は慣れやすい器官と言われていますから、多少の負荷は大丈夫。また、口慣らし練習がある程度進んだ段階で「ネイティブのスピードで言います」なんて言うと、俄然やる気になったりします。短いフレーズから繰り返し練習すれば次第に耳も口も慣れてくるので大丈夫。ぜひチャレンジさせてください。
私たちネイティブ同士でも会話をする時、相手の反応を見ながら、伝わっていないようであれば、繰り返したり、文を短くしたり、スピードをコントロールしたりしながら話しますよね。私たち日本語教師も学習者をよく観察しながら、自身の発話やスピードをコントロールすると良いでしょう。
ティーチャートークに磨きをかけると、より学習者をアトラクトすることができます。学習効率も上がります。学習者をよく観察しながら生のレッスンのライブ感を楽しんでほしいと思います!!



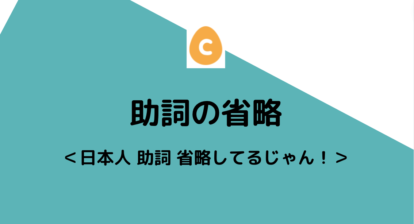
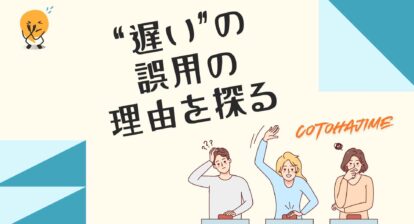
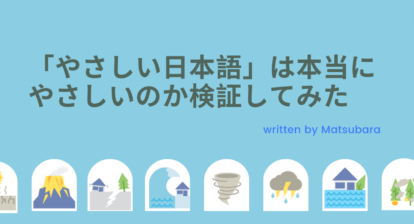


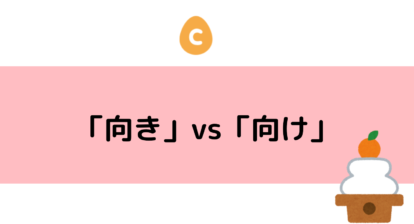
Customer Reviews
Thanks for submitting your comment!