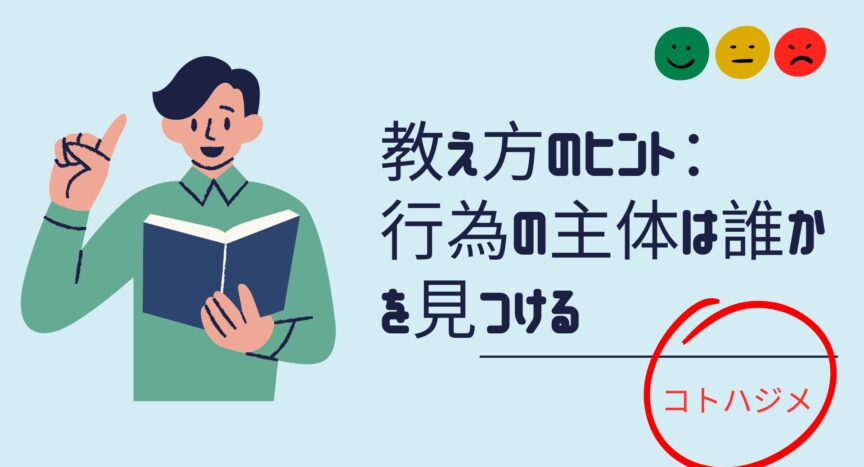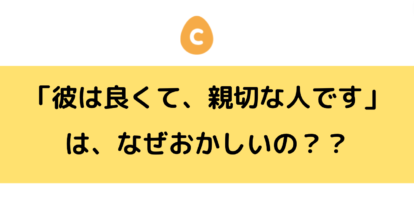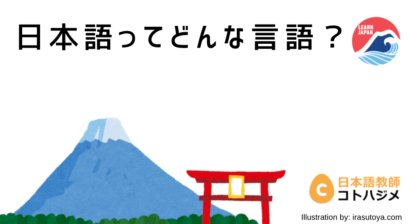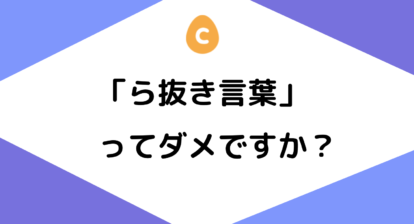Contents
誰がするのか(行為の主体は誰か):学生の質問から講師は成長できる、の巻
教えるヒントはいつも学生から
日本語教師になってまだ2年ほど、日本語能力試験N4対策で、受身・使役・使役受身を教えていたときのことです。
「先生、これ、誰がしますか?(行為の主体は、誰ですか)」
ああ、そうか。使役や受身になると、行為の主体が分からなくなるのか…その質問を聞いて、ハッとしました。
そしてまた、受身や使役に限らず、日本語の文型では行為の主体が見えにくくなる、混乱を招きやすいものが多そうだ。ということは、まずは「誰の行為(アクション)なのか」がわかるよう指導すればよさそうだ、と遅まきながら自覚したのを覚えています。
というわけで、今回は文型別に行為の主体にどう注意を向けたらいいかを考えていきたいと思います。
■受身と使役の場合
受身や使役は助詞の「に」が行為をする人と教えます。
例)
ケーキを子どもに食べられた。(「食べた」のは子ども)
ケーキを子どもに食べさせた。(「食べた」のは子ども)
ただし、
「行く」などの移動動詞は基本文型が「【場所】に行く」と助詞の「に」がすでに使われているため、使役文型内では「を」に付く人が行為の主体者だと教えます。
例)
子どもを塾に行かせた。
そして、大事なのは隠れているが主語は「私」であること、私のストーリーとして語るときにこそ、この文型は出現しがち、なぜなら「受身」や「使役」は話者(私)の感情表現であるからだ、というところも指摘しておきたところです。
あるとき、受身・使役・使役受身の煩雑さ?に嫌気がさした方がいらっしゃり、「私は使役や受身を一切使わない。能動態のみで何でも言えるし(意訳)」と言い切った方がいらっしゃいました。
例えば
子どもが私のケーキを食べた。
で、十分ではないかと。受身を使おうが使役を使おうが「食べた」という事実には変わらないのだから、というご主張です。さらに彼女は言いました。「私は外国人なのだし、それで十分だと」。取り付く島もありません。
それはそうなんだけど…。気持ちが言葉に乗っからないコミュニケーションは、いくら外国語であってもどうなのかなあと思ったりもしました。
この方も、使役や受身を最初に勉強したとき、行為の主体者のマーカー(助詞)に注目し、そこにあるニュアンスや気持ちを理解すれば、きっと使おうと思ってくれただろうに…と思ったのでした。
■使役受身の場合
使役受身は、主格の「は」に付く人が行為の主体者です。
例)
私は、子どものとき、親に塾に行かされた。(「塾に行く」のは「私」)
私は、高校の時、親によく英語を勉強させられていました。「英語を勉強した」のも「私」)
まずはこの二点を指摘するだけでも視点(focus point)がクリアになり、少しは苦手意識がなくなるような気がします。活用形の複雑さにとらわれ、「(当該)行為をするのは誰か」という一番大事な点を見逃す学生が多いという点も講師は知っておくべきですね。
■やりもらい
行為の主体が誰がが見えにくくなる典型といえば「やりもらい」の文型ではないでしょうか。「あげる」「もらう」は、どの言語にもあるはずですが、「くれる」は特殊です。someone gives ME、ものや動作が「私に」向かってくるときだけ使うのが「くれる」だということを指摘すると学生は迷いません。
例)
友だちは私に花をあげました。✕
友だちは私に花をくれました。〇
学習がある程度進んだあと(学習者のレベルが初級後半に来たときにでも)、文型別にこの考え方で以下のように整理してあげるとさらによいと思います。
<わたし(話し手)がする>
機能:許可を求める
~てもいいですか。
~させて ください(くれませんか・もらえませんか +これに丁寧度が加わる表現)。
~させて ほしいんですが。
~たいんですが。
<あなた(聞き手)がする>
機能:依頼する
~てください(くれませんか・もらえませんか +これに丁寧度が加わる表現)。
~てほしいんですが。
導入する際の注意点
最後に許可・依頼の、導入時の注意点ですが、
教える・連絡する・電話する
貸す・借りる
など、聞き手と話し手あるいは第三者の間で、ものやサービスの移動がある動詞は混乱を招きやすいのでやめておいたほうがいいです。
まずは、日本語・英語を話す・書く、コピーをする、などがおススメです。
例)
許可:英語で話してもいいですか(日本語で質問をするのが難しいとき)。
依頼:先生、(ローマ字ではなく)ひらがなで書いてください!(ひらがなを覚えたいんです)。
「写真をとる」という語彙ですが、「写真をとってもいいですか」と「写真をとってくれませんか」では、写真をとるという行為をするのが誰か、文型によって行為の主体が代わる典型例としてとりあげるのはおもしろいかと思います。これに関しては、学習者が日常的にまちがって使うことが多いと聞きます。ほとんどの人が、自分たちの写真をとってほしいときに「写真をとってもいいですか」と言ってしまうようです(なぜだろう?)。
絵カードなどを使い、お寺や美術館で写真をとりたいとき、写真撮影の可否を問うのはどちらの疑問文か、お寺の前で家族みんなの集合写真がほしいとき、近くにいる人に写真撮影を頼むのはどちらかなど、確認するとよいでしょう。