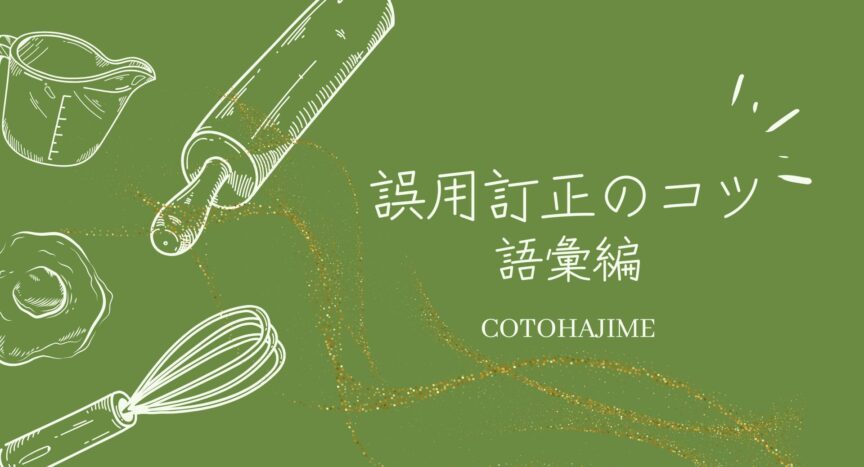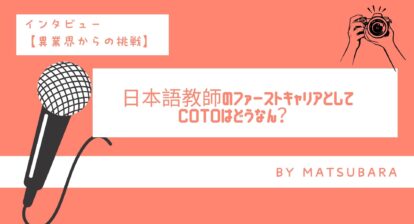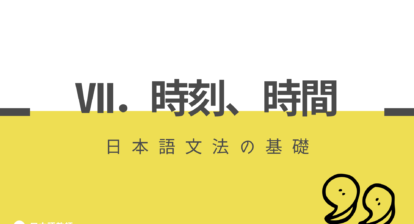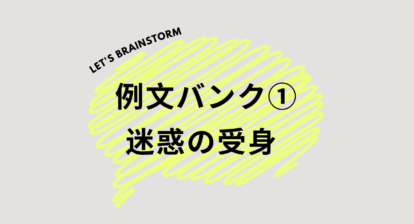誤用訂正のコツ:語彙編
まずは以下の会話文をご覧ください。
<場面>
会社で、ある商品のコピー(宣伝文句)について、アイデアを求められた。
Aさん→中級日本語学習者
Bさん→日本人
※AさんとBさんは同僚である。
A:Bさん、なにかいいコピー思いつきませんか。文字数このぐらいで。
B:う~ん、そうだなあ。✕✕✕ってのはどうでしょう?
A:なるほど。いいですね、それ活用します!
上記の会話で、どこがまちがいか、あるいは変か、わかりましたか。
私は「活用する」という語彙の選択が気になります。
では、この間違いをどう訂正すればいいのでしょう。
今回は、語彙の誤用訂正のしかたについて考えようと思います。どの言語学習でもそうだと思いますが、語彙は中級以降、抽象的な語彙、観念語彙が頻出します。直訳だけでは足りない、理解できない、誤解を生みやすいものがたくさんです。
訂正のステップと方法
まずは先述の例文について、訂正のステップと方法を考えます。以下、誤用のwhy「なぜ」の探り方です。
① 学習者が何を言いたかったのかを考える
場面は会議中、文脈はAさんがBさんにアイデアを求めています。Aさんの「活用します!」は、おそらくはBさんのアイデアに対する受諾であると考えられます。そのような場面で日本人が自然に出る応答なんでしょうか。「それ、いただきます!」とか、それがカジュアルすぎるなら(日本語が母語でない者が使う適切性・安全性を考えるなら)、「それ、使わせていただきます」などではないでしょうか。つまり「活用する」ではなく「使う」という語彙が適切だったわけです。
② 学習者がどうして間違ったのかを考える
学習者の母語は英語です。英語での受け答えを直訳したために誤用が生まれた、とも考えられます。そこで気になるのは、どの語彙を直訳したか、です。その答えについてchatGPTの力を借りたところ、それは“I’ll use it.”ではないかとのこと。useは「使う」なのでシンプルにその語彙を使えばよかったのですが、ビジネス場面でのやりとりだったため、もっと改まった表現、漢語にすべきだと思ったのでしょう。そこでto use, to utilizeの翻訳として並んでいる「活用する」を選んでしまったのではないかということも考えられます。
訂正のステップ(例)
- 「活用します」が間違いであることを指摘します。
- 正しい言い方の一例「それ、使わせていただきます」を教えます。
- 時間と余力(講師・学生ともに)があれば、なぜ「活用する」はだめなのかを教えます。
「活用する」は、なぜだめか
「コロケーション」という概念を使って教えよう
学生にとっていちばんわかりやすいのは、「活用する」といっしょに使う語彙=コロケーションについて述べることです。
例:古着/空き家/(シルバー)人材/システム/資源…などを活用する
例文からわかるとおり、「活用」は本来の使途・用途とは異なる使い方をしたり、既にある資源、リソースを有効利用することです。
また、いま生まれたもの、最初にあげた会話内の「(その)アイデア」というspecific(特定の)ものといっしょには使えません。
「フォーマル度や硬さ」という側面も気にかけよう
フォーマルな場面、書き言葉など硬い表現を使うべき場所では、一般的に漢語語彙の使用がふさわしいのですが、実はとりあげた会話文の例のように「使う」という和語が正解のこともあります。学習者は漢語=フォーマルと思って過剰適用することがあるということも頭の片隅においておかなければなりません。
おまけ
活用、応用、利用、使用、運用、実用…etc.「用」を用いる語彙はとても多く、この中の語彙の意味と用法についてはコロケーションで考える(教える)のが日本語教育としてはもっとも有効だと考えています。
初中級あたりでいちばん多く聞かれるのが、「使用」と「利用」の違いです、そして誤用も多いので、コロケーションをもちいた説明のしかたをご参考までに提示しておきます。
使用:機械や器具、場所など物理的なものに使う
例)
いま、会議室/トイレは使用中です。✕利用中です。
最近はガスストーブを使用しています。✕利用しています。
利用:サービスや抽象的なものに使う
例)
ATMはご利用いただけません。✕ご使用いただけません。
会場までは、電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。✕ご使用ください。
※サービスを提供しているところ、例えばコンビニ、図書館、プールなど身近な語彙を出すと学習者にはわかりやすいようです。
なお、初級前半で教える「使う」ですが、上記どの例文でも「使う」に置き換えられます。とても汎用性の高い語彙であるため、初級で導入するのだとも言えます。
「✕✕語を使う:仕事で英語しか使わない、日本語を使う機会がない」など、「言語」については「使用する」にも「利用する」にも置き換えられません。物理的なものでもなく、また観点的なものであれ、便利であるから使うというわけではないからでしょうか。これもまたおもしろいところですね。