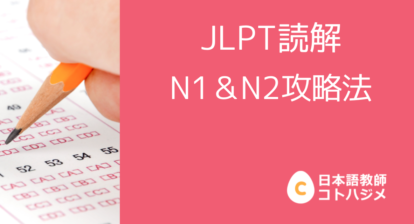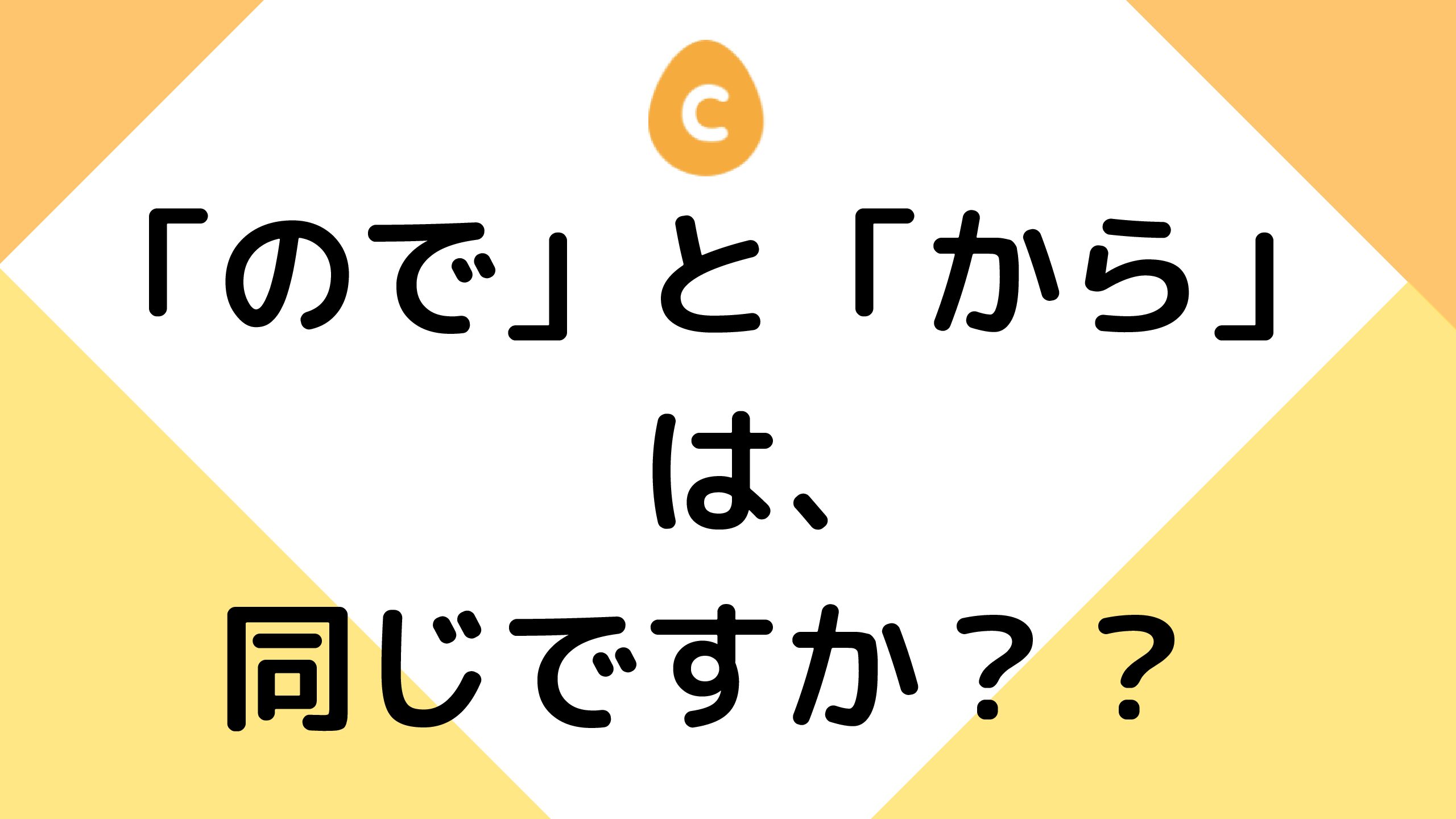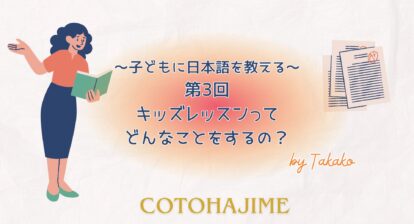Contents
【罠だらけ!?】日本語の授業でロールプレイをする際のコツと注意点
ロープレについて語る第2弾
日本語の授業でのアクティビティの定番「ロールプレイ」。定番ゆえに、私なんかは「やるのが当たり前」と特に疑問にも思わずロープレを取り入れてきました。
そこで「なぜロールプレイをするのか?」と、あらためて意義や目的を考えてみたのがこちらの記事です。
今回は、コトハジメ編集部のライター二人(Hidari先輩&Matsubara)がロープレについて語り合う第2弾となります。授業でロープレをする際に難しいと感じていることや、工夫していることなどをシェアしていきます。
ここで、ライター二人のバックグランドを少し紹介させてください。
Hidari先輩は、Cotoでもよく使用するテキスト『Fun&Easy』の著者の一人。Coto麻布校(対面)で日本語を教えており、豊富な日本語教育の経験をお持ちの講師です。
わたくしMatsubaraは、Cotoではオンラインで日本語を教えております。パラレルワークとしてやっている企業研修でもロールプレイを取り入れることがあり、ロープレの有効性と難しさをいつも感じている次第です。
このようなバックグランドが違うライター二人ですが、告示校での勤務経験があるという共通項があります。
前提:まずは基本をやりきってこそ
Matsubara(以下M):Cotoの勉強会でロールプレイのやり方について最初に学んだとき、すごく丁寧にやるんだな〜と感じました。具体的には、まずは教材に記載のフレーズをスラスラと言えるようにすること、何も見ないで言えるようにすること、声の抑揚や間などを実際の会話に近い自然なものにすること、最後に自分自身の言葉で表現すること、などです。習熟度を確認しながら、Step by Stepで難易度を上げていく…。
Hidari先輩(以下H):ロープレというと、各学生の個性を出すこと、臨機応変な会話ができることが求められているに思われるのですが、実はひねりのないベタな芝居ができることこそが大事なんだと思います。それはつまらないかもしれませんが、まずは基本をやりきってこそロールプレイをやる意義があると私は思っています。
M:私もベースができていない場合は、むしろロープレをしない方がいいのかなと思います。ロールプレイの意義がなくなってしまうので…。
ロープレの「難しさ」と「工夫していること」
①意図や指示の伝え方について
M:ロープレをするときに難しいと感じることは何かありますか?
H:こちらの指示や意図が通じないときです。もちろんこちらの力量が足りないのはひとまず置いて、学生の人数(告示校だと10人以上は普通、Cotoだと多くても8人)や日本語のレベル、学習態度や意欲など、いろいろな要素に作用されることが多いのがロールプレイの最大の難しさだと思います。
M:そうですね。おっしゃる通りいろいろな要素に作用されるので、実は教師の負担も大きいのがロープレだと思います。
特に指示がちゃんと伝わらないと、あらぬ方向に授業が進んだり私語が増えたりして、コントロールが一気に難しくなります。告示校のような人数が多いクラスだと、意図や指示を正確に伝えるのがより難しいと感じますね。
私はCotoではオンラインで教えていますが、ブレイクアウトルームを使うと、自分が見ていないペアの様子は全然わかりません。教師によるフォローが遅くなってしまうことになりますから、ロープレの前に指示や意図を正確に伝えないと、学生は何をどうしたらいいか右往左往して、レッスン自体の満足度が下がります。
H:本当に講師の指示の仕方は重要ですね。いわずもがなロールプレイの文脈、ロール(役割)は一般的であるべきかと。
M:どんな工夫をされていますか?
H:シンプルな指示をすること、そして視覚情報でも伝えることは必須ですね。注意点などは、ホワイトボードにも書くようにしています。
あと、つい忘れがちなのですが、「今から7分でお願いします」など制限時間をしっかり設けることも大事ですね。これもホワイトボードに板書します。
M:時間制限を明確にすることで、いい意味で緊張感を持たせることができますしね。
H:視覚情報でいうと、ロールカードを持たせるなど、物理的素材があることも有効だと思います。
M:ロールカードは便利アイテムですよね。ロープレが苦手な学生にとっては、指示がしっかりと伝わる以上の意味があります。カードが心の拠り所になるというか、心理的なハードルを下げるのにも役立っているようです。
わたしは企業研修でもロールプレイを取り入れることがあるのですが、そこで使うロールカードには、演じる役の性格や立場と、「必ず言ってほしいセリフ」が書かれてあるんです。悪役(クレーマーなど)や、自分とは全然違う性格・立場の人役をやっていただく場合は、ロールカードは特に有効だなと感じます。このロールカードに加えて、講師によるロープレ前のプチ演技講座があれば、かなり失敗のリスクは下がります。ゼロにはなりませんが。
②教師の観察眼とフィードバックについて
M:学生同士のロープレが始まったらどのようにしていますか?
H:必ず各ペアやグループを頻繁に見回ります。そこで質問を受けたり(語彙の補完が多いですが)、聞こえた文法の間違いをすかさず直したりしています。
M:ロープレ中に学生同士で会話がどんどん広がるのはいいことですが、その際に生じる「日本語が出てこない…」「不自然な日本語になってしまう…」といった起きやすい問題に対処されているわけですね。
H:はい。それからいい運用ができているペア・グループをほめることも忘れません。ここでいう「いい運用」というのは、あいづちなどのクッションワードが入っていて会話が自然であるとか、既習文法をいくつか組み合わせて、なるべく長い文で話そうとしているとかです。
M:学生のモチベーションアップにもつながりますね。私も学生の立場でロープレした際、その場で先生に褒められた時のことはけっこう記憶に残っています。
H:あと、時間があれば発表もさせています。私はこれを勝手に「パフォーマンスタイム」と名付けています。そして、語彙や大事な文法など共有すべきものがあれば、最後に説明します。
M:学生個人がもっている個人知や暗黙知を全体にシェアして説明することで、集合知化・形式知化することにもなりますね。
③ペア決めについて
M:以前、ロープレのペアを組ませたら、どうやらその学生同士がけんか中だったらしく、やりたくない!と騒ぎ始め、授業が中断したことがあります。「いや、そんな個人的なこと知らんがな!」って感じですが、そんなこともあって、「誰と誰を組ませるか」についてはけっこう慎重です。ペアを組む相手とあまりにもレベルやモチベーションが違うと、レベルが高い方・積極的な方が不満を持つでしょうし…。
H:私はペアをつくるときは、その座組についてあまり考えすぎないほうがいいのかなと思っています。この人とこの人はレベルが違いすぎるとか、国情や世情的に組ませて大丈夫かしら?とか考えているとキリがありません。
あるときから、私は人数の多いクラスではペアはくじ引きなどで決め、偶然の出会いで生まれるエネルギーのほうに期待するようになりました。
M:ペア決めに公平性・偶然性をもたせているんですね。毎回同じペアになることはないですし、おっしゃる通り偶然の出会いによる化学反応って、実際の日常の会話でもよくありますよね。「たまたま隣の人と世間話をしたら、気が合って仲良くなった」とか「話す必要性があったから仕方なく話したけど、思っていたよりいい人だった」とか。会話や対話の本質を見た気がします。
教師の心構え
M:最後に、ロープレをする上での教師の心構えについて伺いたいと思います。
H:ロールプレイは、演じることが苦手な学生にとっては地獄です。そのことをまず講師側は忘れないことが心構えとして大切だと思います。
M:そもそも自己表現が好きではない学生もいますからね。私自身は自分の考えを他者とシェアしてワイワイやりたい人間なので、こういう自分とは違うタイプの人たちのことを忘れがちです。
H:私は不必要に盛り上げようとせず、淡々と指示を伝えるようにしています。その時点であまりにも場が温まっていないようでしたら、与えすぎない程度に会話の入り口のヒントをあげてもいいかと思います。
M:ロープレは、時に予想以上に盛り上がり、学生たちが「授業楽しい!」「話せて嬉しい!」「仲良くなって最高!」という反応を見せてくれることがあります。ただそれは、瞬間最大風速みたいなものだと思います。いろいろな好条件が整ったときのみ発生する「ラッキーイベント」のようなものかと。
あまりにこの盛り上がりに期待しすぎると、教師側にも変な力が入ってしまう…。おっしゃる通り、淡々と進めて、「あ、今日の雰囲気じゃダメかも…」と思ったら、無理にやらないという臨機応変さも必要かもしれませんね。