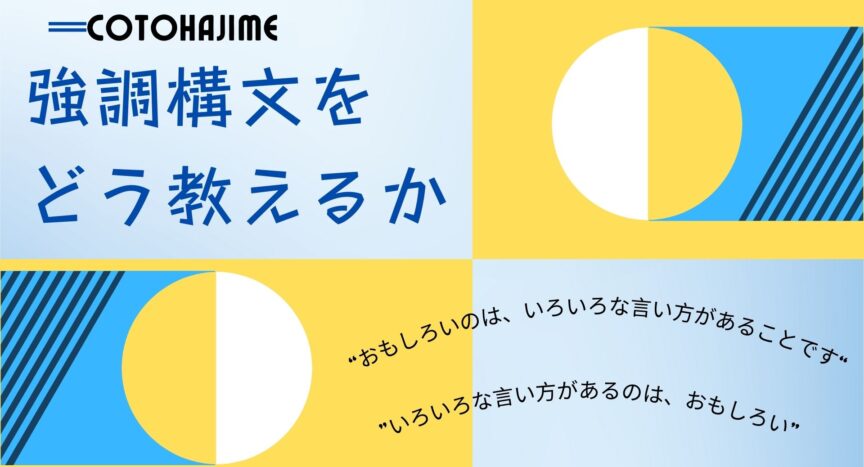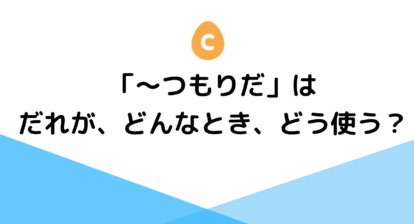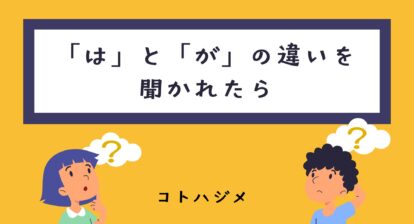Contents
強調構文をどう教えるか。
①私が生まれたのは中国です。
②私は中国で生まれました。
文型でいうと、①は強調構文、②は平叙文ですが、どちらの文からも伝わる情報は、話者が「中国生まれ」だということ、その点では同じです。
ではなぜ①のような言い方をするのか。それは強調構文がいわゆるレトリック(倒置、反復、比喩というような修辞的なもの)の一つであり、別に使わなくてもいいが、使うとより印象的になるからだと言うことができるでしょう。
外国語を学習する過程では、類似した意味を持つ、さまざまな構文の存在や、それについて教えるとき、話者の心理や文脈も併せて考えることが必要です。伝え方の多様性は言語の豊かさでもある一方で、裏を返せば言語の不経済性(=uneconomical、非効率的)とも考えられがちです。とりわけ学習者にとっては、単純に覚えることが増えるということですから、「また他の言い方?!」「似たような文型がいくつあるの?!」「全部覚えなきゃダメ?」と内心穏やかではない気持ちもあるはずです。
とはいえ、①のタイプの強調構文は、どの言語にも存在するはずですので、順を追ってそのレトリックを使うのが必然!と思わせるところまでいければ、どの学生も自然に納得し、理解し、使うことができるようになるのではないかと思います。
というわけで、一例ですが、導入のパターンを考えてみました。
Ⅰ 隠れた意図に注目:対比/意外性を強調する
会話例を出して導入する
1)
A:お国は?
B:アメリカですが、生まれたのは中国です。
※国籍と出身地が違う、その対比をさせるため強調構文を使う。
2)
私のうちは寿司屋です。
でも、私が好きなのはパンなんです。
よく食べるのは、パンなんです。
※稼業と嗜好の違い、意外性を強調するため強調構文を使う。
Ⅱ 強調構文をよく使う「文脈(ここでは自己紹介:スピーチ)」で理解させる
私はスポーツが好きです。見るのも、するのもすきです。
・一番よくするのは、フットサルです。
・一番よく見るのは、サッカーです。
・一番好きなのは、ボールスポーツです。
※generalな話題から始めて、細分化し、それを自己紹介というレトリックが必然的に使われる文脈で使わせてみる。
Ⅲ その他の強調構文(~のは、~ということです:述部が名詞句になるパターン)
<導入>
いつかアメリカで大リーグを見たいと思っているんです…(でも簡単じゃないと思っています)。
問題(障壁)がたくさんあるのです。たとえば、
・チケットが買えるか(非常に人気があるので)
・チケット代が払えるか(高いはず)
・休みがとれるか(日本では長い休みをとるのが難しい)
…etc.
<文作>
問題なのは(難しいのは)、
・まずチケットが買えるかということです。
・そのチケット代が払えるかということです。
・(なによりlast but not least”)休みがとれるかということです。
※この文型は、英語でもThe thing is…、とかThe problem is…とかThe most difficult thing is…などのパターンがあるので理解は難しくないかと思われます。
誤用がでたら、こう直す
- a) 東京の夏の天気なのは、むし暑いことです。
- b) プレゼントの予算なのは、800円です。
上記のような誤用が出た場合、どう直すのがいいでしょうか。
<訂正案>
「~のは~ことです。」という文型の最初の「~」に入るのは、「東京の夏の天気」「プレゼントの予算」などの普通名詞ではダメです。物理的な形を持たない概念や状態、感情などを表す抽象名詞(問題the problem、難しいのthe difficult thing、悲しいのはthe sad partなど)でないといけません。
なので、直すとすれば(学生に意図するところを十分聞いてからですが)
a) 東京の夏の天気なのは、むし暑いことです。
→ 東京の夏で大変なのは、むし暑い(暑すぎる)ことです。
b) プレゼントの予算なのは、800円です。
→ プレゼントで問題なのは、予算が800円しかないことです。