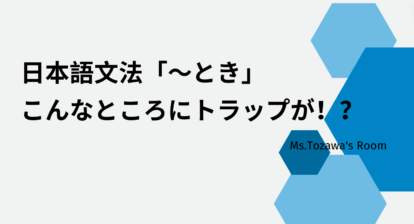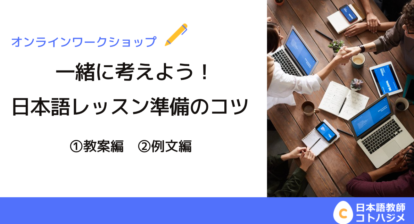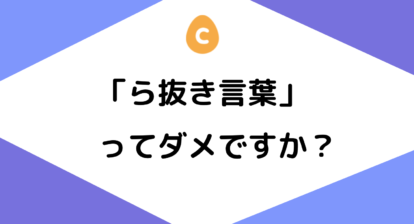Contents
「空気読んで…」高コンテクスト文化の利点と弊害
先日、仕事の関係でとある企業の採用担当の方とお話しする機会がありました。
雑談の中で、どんな人材を採用したいのか、どんな人は採用を避けているかなどを聞いてみたところ、その方曰く「前職が教師とか講師とか名の付く職業だった人は、採用を見送りたいですね〜。プライドは高いし、話し方はエラそうだし、素直に謝らないし、使いづらくて…」と。どうやら職場でいろいろ問題があったようで、私の質問をきっかけに悪夢がよみがえったようでした。
おやおや、それは一般化のしすぎでは?一応私も教師と名の付く仕事をしてるんですけど?バリバリのサービス業界出身だから、自分が悪くなくても頭を下げるなんて慣れっこですけど?
…なんて一瞬思いましたが…、正直に申し上げます…。私自身も教師と名の付く職業の人に対して、話し方が高圧的でキツイな〜と感じたことがあり、何人か顔が思い浮かんだのでした。
一応擁護すると、これは普段、自分より立場が下の人と接する機会が多いことや、ストレートに言わないと相手に伝わりづらい職場環境なども影響しているのではないかと思います。
はっきり言わずに学生に察してもらおうとすると、意図を察してくれず、イライラすることになるでしょうから、強い言い方になるのは理解はできます。
教師や講師と呼ばれる人がいる場所は、「空気を読む」「察する」ことで言葉にしなくても阿吽の呼吸で意思疎通できる高コンテクスト文化を前提とすると、仕事にならないのかもしれません。
さて、私たち日本語教師も、教師とか講師とかの枠に入ります。ただ、相手は日本語ネイティブではありません。暗黙の了解が成立しない低コンテクスト文化を背景に持つ学生さんも多くいます。日本語教師として、異文化を背景に持つ学生に対して配慮するべきことがありそうです。
また、このグローバル時代に高コンテクスト文化の負の側面が目立つようになってきましたが、正の側面はないのでしょうか。
というわけで、今回は高コンテクスト文化の正の側面と負の側面を踏まえながら、日本語教師として気を付けたいことを考えてみたいと思います。
高コンテクスト文化の正の側面
「言繁し しばしは立てれ 宵の間に おけらむ露は いでてはらはむ」
これは、私が最近見た歴史解説系のYouTube動画で紹介されていた和歌です。嵯峨天皇皇后の橘嘉智子が詠んだ歌とのことです。
現代語訳:「人の噂が煩わしく存じます。あなた(天皇)はしばらく曹司に入らず、外でお立ちになってお待ちください。宵の間にお衣についた露は、私が後ほど出てお払い致しましょう」と。
…つまり。「他の女房・側室たちから嫉妬でいろいろ言われるのがウザイから、あんたはアタシの部屋に入ってこないで、外で待っとれぃ!」ということですね(意訳がヒドイ…)。
もちろん天皇を外で待たせるなんてありえないので、遠回しに「今は来ないでください」と伝えているわけです。周りからの嫉妬に患う様子や、相手に対する申し訳なさが、暗に、しかし強く伝わってくる和歌だなと思いました。
ド素人の私が言うのもなんですが、和歌には「察する」「暗に伝える」美しさがあると感じます。和歌に限らず、芸術がもつ美しさや儚さといった趣は、高コンテクスト文化とは切っても切れない関係なのではないでしょうか。
また、「察する」「空気を読む」文化は、日本のおもてなし文化を支えているとも思います。言わなくても望むものが出てくる、かゆいところに手が届くといった素晴らしいおもてなしは、マニュアル通りにこなすだけではできません。おもてなしされる側の高い満足度は、「言葉にするのは野暮」という高コンテクスト文化と結びついているはずです。
他には、コロナ禍で多くの人がマスクを着用したり、自粛をしたりしたのも、「空気を読む」「阿吽の呼吸で意思疎通する」土壌があるからこそできたのではないでしょうか。
高コンテクスト文化の負の側面
高コンテクスト文化の負の側面として、情報が正しく伝わらない、自分の意思や気持ちが通じない、相手が慮る・察する能力が低い場合はイライラする、コミュニケーションが成り立たない!(笑)
いくつか例を挙げます。
情報を正確に伝え、正しい行動を取ることが求められる災害時は、あいまいな表現を避ける必要があります。「察する」ことを求めている場合ではありません。
下記の記事では、やさしい日本語を検証しました。やさしい日本語は、日本語非ネイティブが具体的な行動を選択できるよう、難しくあいまいな言葉を使用せずに作られていることがわかりました。
最近、「お役所言葉」を一般市民でも分かる言葉に変えていこうとする動きが出てきています。せっかく作成した文書が読み手である市民に伝わらなかったり、誤読を招いたりする。これは「言わなくても分かって」「文脈を読んで」という文化が、その要因の一つになっているようです。
「松阪市の広報紙で保育士を募集した時に『潜在保育士』と表記したら、市民から『分かりにくい』との声があった」(三重・松阪市がお役所言葉返上 特別徴収は「引き落とし」日本経済新聞)ということで、分かりにくい用語の変更のほか、「できるだけ」や「可及的速やかに」など、あいまいな表現や分かりにくい言葉を使わない、「社協」や「生保」などの略語を使わない、とも手引きにありました。
また、察することを相手に求めることで、人間関係が悪化することがあるのも問題です。下記の記事では、回りくどい伝え方が持つ攻撃性について述べました。
他に、高コンテスクト文化の負の側面として、「同調圧力」や「本音と建前」などがありそうですが、挙げればキリがなさそうなので(笑)、ここでこの話は終わりにします。
日本教師として注意するべきことは?
まず、日本は高コンテクスト文化だ!欧米は低コンテクスト文化だ!など、あまりに固定的に考えることは、文化のステレオタイプ的な見方につながる恐れがあります。日本文化=高コンテクスト文化と固定化すると、学習者にも「察すること」「空気を読むこと」を求めてしまいそうです。
その上で、やはり「察する文化」「慮る文化」は間違いなくあるので、日本語教師としては学生が巷の日本人とコミュニケーションを円滑にとれるよう、指導・サポートは必要かなと思います。
「今は自分の意見をしっかり言語化することが求められている時代だから」と、一般的な日本人が不快に感じるであろうストレートすぎる表現を見て見ぬふりをするのは、学生が気の毒です。「こういう言い方もありますよ」「こんな言い方の方が私は嬉しいかな」と教えられるのは教師だけでしょう。
実際にCotoでもよく使用する『げんき』や『Fun&Easy』のテキストにも、誘いを断るシーンなどに「その日はちょっと…」といったやんわりした表現が記載されています。高コンテクスト文化を考慮したテキストの記載はいろいろなところで見られます。
また、教師の自己検証も大切だと思います。学生があまりにストレートな言い方をしている、または回りくどい言い方をしているのは、教師の影響を受けている可能性があるからです。
教師は日本語の分野において、見本となるポジションですから、自分が発している言葉には常に敏感になっていたいものです。
教師の自己検証についてはこちらの記事でも触れましたので、ご参考まで。
中道って意外と難しい?!
ここまでエラそうに書いてきた私ですが、私自身も、相手に配慮しながらも率直なコミュニケーションをする=中道なコミュニケーションをする難しさを感じております。
最近こんなことがありました。
Zoomミーティングに参加していた時のこと。自宅から参加しているあるメンバーにみんなが苦笑い。
というのは、そのメンバーの同じ部屋にいると思われる家族の声が本人の声よりも大きくはっきり入っていたからです。ミーティングがやりにくい上に、プライベートが丸わかりで、気まずい雰囲気が…。
気を利かせた別のメンバーが、「なんか…大丈夫ですか?」「話さないときは、ミュートにしてもいいんだよ?」など、やんわり伝えるものの、当の本人は「大丈夫大丈夫〜、なんか息子が〜、夫が〜」と話し始め、(いや!そういうことじゃないんだよ!)(気づけよ!)と周りのイライラが高まっているのを感じました。
いたたまれず、私も「ごめんなさい…。ご家族?の声が入ると、発言者の声とかぶって聞きにくいから…」と、やっと声を挙げ、なんとなく場が収まったのでした。
いや〜、伝え方って難しいですね。。