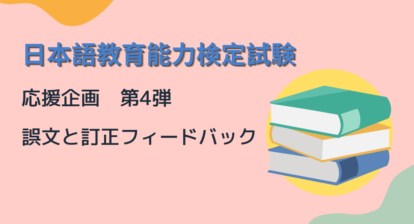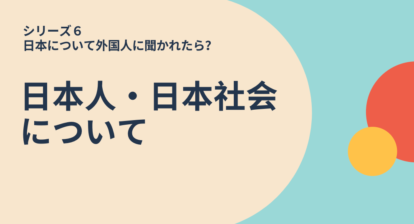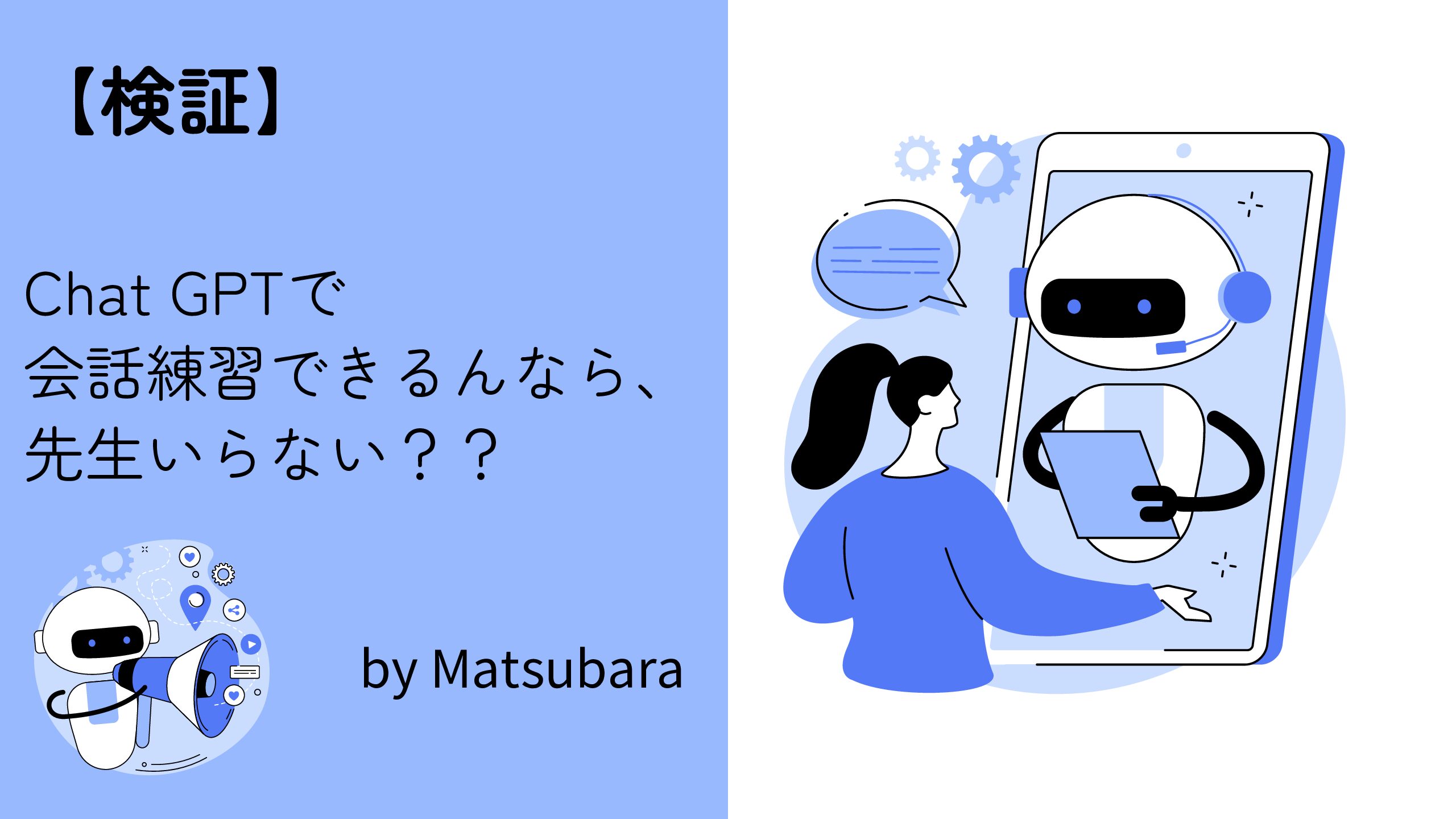非漢字圏の学習者へ、漢字をどう教えよう?
非漢字圏の学習者の中で、日本語のゴールを中級以上に設定するなら、漢字学習は絶対に避けられない大きな関門のひとつです。もともと漢字のフォルムや表意文字であることへの興味などがあれば別ですが、ひらがな・カタカナを覚えたあとに第三の表記法として、2000以上の漢字が待っているという現実にひるまない学生はあまりいないのではないでしょうか。
では、私たち教師は、そのような学生にどう寄り添い伴走していけばいいのでしょう。
そこでまずは学生の漢字アレルギーを最小限にすることに注力するのが大事です。また、中級以降は語彙の量がかなり増えますから、その語彙量に立ち向かえるのが漢字であるという認識を講師側は忘れないようにしたいものです。漢字を覚えれば、より語彙が覚えられ、語彙が覚えられれば、より漢字が覚えられる。漢字力と語彙力の相関関係は非常に強いのです。
まずは私たち自身が思い込みを捨て、視点を変えてみよう。
私たちは教授法で学んだとおり、日本人の子どもに教えるように外国人に文法を教えることはできません。私たちが受けてきたような国語教育というところからは、外国語としての日本語教育は離れなければならない。そのことは百も承知。なのですが、こと外国人への「漢字」教育となると、私たちはそれを忘れがちになってしまいます。
そこで注目すべきは、なぜ彼らにとって漢字を覚えるのは難しいのかというシンプルな問題提起。非漢字圏でも、努力をすれば覚えられる人と、そうでない人にはどのような違いがあるのでしょう。それはまず、覚えられない人たちにとっては、字がただの「塊(かたまり)」にしか見えていないからだと思われます。
塊をどう切り分けよう?
分解法①
ブロックに分ける(へん・つくり・かまえ・かんむりetc…という呼び方ではなく)、学生の視線をどこに向けたらいいかを考えるやりかたです。以下まずは大きくは3つで考えます。
1)左/右 時(日+寺)※いわゆる「へん」と「つくり」に分けてみるやり方です。
2)上/下 台・食 ※いわゆる「かんむり」とその他のパーツで見る方法。
3)外/内 国 ※いわゆる「かまえ」とその中身に分ける視点。
その他の視点としては、大、日、月、火、水、木、金、土など、他の漢字の構成素として使う頻度が多いものは、初級のうちからしっかり入れておくのが大事です。
分解法②
漢字の構成素として、既習漢字やカタカナに注目させるやりかたです。
●カタカナが入っている漢字の例: 事(ロ、ヨ) 名(タ、ロ) 曜(ヨ、イ)など、よくよく見ると隠れているカタカナはたくさんあります。学生に見つけさせるのもいいかもしれません。また、板書するときに、色分けをするなど、漢字には既習の文字が隠れていることを認識させると、かなり定着が上がると思います。
●既習漢字が入っている漢字の例
・日day+月moon=明るい
・火fire 燃える(熱いものに、点々が多いことも指摘できるかも)
・水water 氷 泳ぐ
・木wood 林、森、休
・金gold 金銀銅
・土soil 地 など
分解法③
語彙から導入する:これは分解法というより導入法ですが、既習語彙から漢字を入れるやり方です。この方法は、ゼロレベル以外、どのレベルでも可能で、語彙と漢字が密接に関連していることを学習者に認識させることができる、漢字へのモチベーションに刺激を与えることができる大切な方法の一つです。
例)
①<べんきょうする>
べん きょう する
音は「べん」と「きょう」に分かれ、その一つ一つに漢字がつく。「べんきょう」という語彙の構成漢字が2つであることの認識をさせます。
それから、一つ一つの漢字について意味を伝えていきます。
勉 強 →勉 to make an effort、強い strong 強く「がんばる」ことが「べんきょう」であるという解説ができるかと思います。
②<しごとする>
し ごと する
仕 事 →仕 to serve/commit 、事things(work)
中級以降はどうするか?
中級以降は、初級以上に語彙と漢字のリンクを強く意識した指導が大事です。会話が上手なのに今まで文字をまったくやってこなかった人は今さら漢字…と思いがちですが、実はアドバンテージがあります。語彙が多い人には漢字学習を促すことでさらなるレベルアップチャンスが広がることも指摘したいところです。
漢字の指導法については、以下も参考になさってみてください。
「途中で心が折れない楽しい漢字学習」