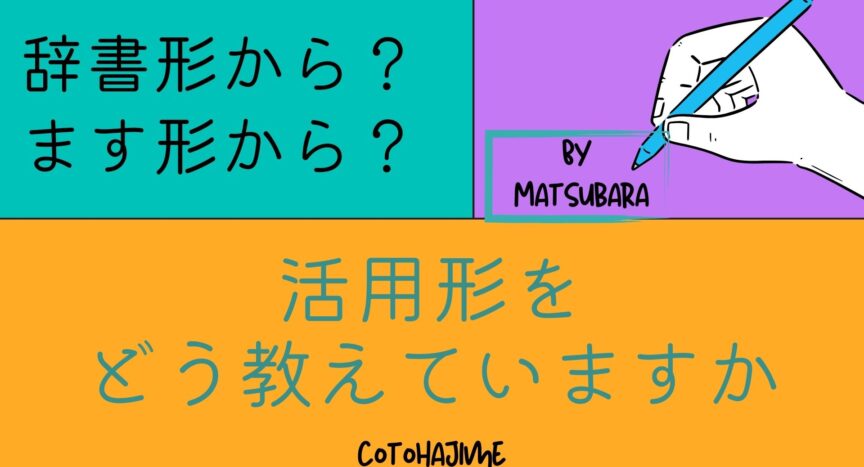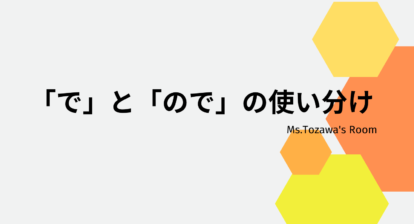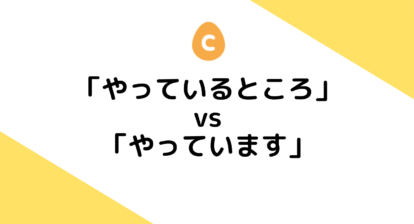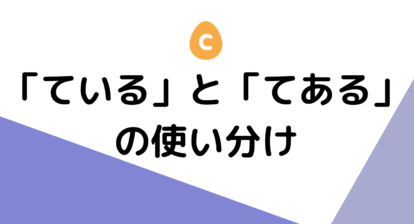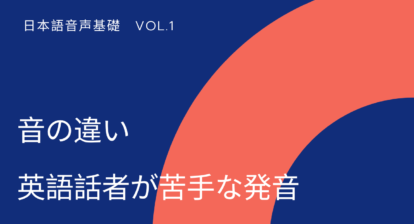Contents
活用形を教える あなたはどっち派?「辞書形」VS「ます形」
「辞書形」の『GENKI』VS「ます形」の『みん日』
今回のテーマは「辞書形」と「ます形」での活用形導入についてです。後半は、コトハジメ編集部のライター二人(Hidari先輩&Matsubara)の対談形式でお届けします。
「辞書形」での活用形の代表的なテキストとして『GENKI』、「ます形」で活用するテキストの代表格として『みんなの日本語』があります。
私が日本語教師になって初めて使ったテキストが『GENKI』でした。その後、告示校でも教えるようになり、そこで『みんなの日本語』を使うことになったわけですが、教え方の違いにちょっと戸惑ってしまいました。
この2つを比較すると、動詞のグループ分けについての理解が深まり、「て形」「ない形」など活用形の導入法の違いや、留意点も明確になると思います。
動詞のグループ分けの違い
活用形を導入する前に、まず動詞のグループ分けには3種類あることを学生に教える流れが一般的かと思います。
『GENKI』では、U-verb、Ru-verb、Irregular-verbと表記されていて、『みん日』ではⅠグループ 、Ⅱグループ、Ⅲグループとなっています。
『GENKI』では、3課で最初に動詞のグループ分けについて触れています。しかし、Cotoでは、て形導入に際して、しっかり動詞のグループ分けを導入するのが望ましいと考え、6課からグループ分けの概念を教えます。
私の場合になりますが、「U-verb、end with U。Uの前、vowel、A or U or O」「Ru-verb、end with RU。RUの前、vowel、I or E」「Irregular-verb、する・くる only two!」のように非常にシンプルな英語を使い、スライドを見せながら辞書形(dictionary form)で導入しています。なお、Ru-verb→Irregular-verb→U-verb→Exception(例:入る、帰る)という流れで教えています。
一方『みん日』では、新出単語は「ます形」で表記されています。動詞のグループ分けは14課からで、動詞にグループが表記されるようになります。そしてこの課で「て形」が導入されます。
「ます形」でのグループ分けはこんな感じです。
- Ⅰグループ:ⅡグループとⅢグループ以外の動詞。「ます」の前が「い」段の動詞
- Ⅱグループ:「ます」の前が「え」段。例外として「い」段の動詞が9つある
- Ⅲグループ:します・きます
「ます形」の導入も同じくⅢ→Ⅱ→Ⅰと、Iグループは最後に教えることがメジャーなようです。
活用形の導入の違い
可能形(potential form)、意向形(volitional form)、使役形(Causative form)など、活用形が出てくるたびに、「辞書形」で入るか、「ます形」で入るか違いますが、ここでは早い段階から出てくる「て形」と「ない形」で比較してみることにします。
例1)「て形」導入の違い
「て形」導入は、『GENKI』では6課、『みんなの日本語』では14課で、どちらも動詞のグループ分けを学んでから、「て形」に入る流れとなっています。
「て形」を覚えるための歌もありますが、その歌詞が違います。
♪普通形から入っている歌♪
「うつる→って~♪ むぶぬ→んで~♪」でお馴染み、カントリーロードの替え歌です。
【初音ミク】て形の歌 げんき / 【Hatsune Miku】Nihongo Te-form song Genki U-verb & irregular verbs
ちなみに以前、アニメ好きの学生が多い授業で、トトロの替え歌を紹介してみたのですが、思いのほか学生が知らなくて、結果は散々でした。。
てけいのうた 2019( te-form song て形の歌 tekei no uta )みんなの日本語14課 となりのトトロ(My Neighbor Totoro)「さんぽ」より JLPT/N5
♪ます形から入っている歌♪
「いちり→って、みにび→んで~♪」と、キラキラ星のメロディーに合わせて歌います。
★カラオケあり★にほんご てけいのうた (て-form song “Twinkle Twinkle Little Star” with Karaoke)
例)「ない形」導入の違い
『GENKI』で「ない形」の導入は8課です。
U-verb:例)行く(Ku)→行か(Ka)ない。Only vowel change, add ない。 Exception、あう→あわない、ある→ない
Ru-verb:る change to ない
Irregular-verb:する→しない、くる→こない
Ru-verb→Irregular-verb→U-verb→Exceptionという順番で教えています。
『みん日』での導入は17課です。
Ⅰグループ:「ます」の前の母音「i」を「a」に変更して、「ます→ない」と接続 +例外(すいます→すわない)
Ⅱグループ:「ます」を「ない」に変更
Ⅲグループ:します→しない、きます→こない
なお、『GENKI』ではExceptionの「ある→ない」はここで一緒に教えますが、『みん日』では「ありません→ない」は、この17課ではなく、20課で教えることが多いようです。
教師&学生にとっての活用形
教えやすいのはどっち??
Matsubara(以下M):ここからはコトハジメのライター二人が、徒然なるままに語り合いたいと思います。
私は最初に使ったテキストが『GENKI』ということもあって、辞書形での導入の方が教えやすいなと感じます。Hidariさんはいかがですか?
Hidariさん(以下H):私はどちらでも大丈夫、かな。養成講座では『みんなの日本語』=「ます形」、その後Cotoでは『GENKI』=「辞書形」でした。最近、Cotoにも中国語話者の学習者が増えてきていますよね。中には英語があまり得意ではない学生もおり、その方々には『みん日』を使っているので、両刀使いといっていいかと思います。
M:私は『みん日』歴が短いので(というか日本語教師歴が浅いので)、活用形を教えるときは、「え…これで教え方大丈夫だよね…」と、文法書などでの確認は必須ですね。「同じ活用形なんだから『GENKI』と同じだよね」と調子に乗っているとイタイ目に遭います。。
それぞれのメリット&デメリットは?
M:辞書形で導入するメリットは何だと思いますか?
H:初級でも中級以降も辞書形を含む普通形と接続する文型が多く出ます。そして、『GENKI』のほうが普通形活用の出順が早いので、動詞の活用形を覚えることで使える文型が増えるということに気づいた人、プラクティカルな考え方をする人や論理的思考型の人は伸びやすいし、学習に加速がつく気はしています。
M:たしかに、普通形(辞書形を含む)をベースとした文型は多いですね。逆にデメリットはあるでしょうか?
H:辞書形から活用を覚えた学生は、早い時点で自分の知らない間に誰にでも、時と場合を選ばず「ため口」をきいてしまっている、というデメリットはあるかと思います。先生にも知らない間に「ため口」で話してしまっている…。
M:ということは、それと反対なのが「ます形」をまず覚えるやり方ですね。
H:はい。概して、外国語学習の場合、初級であればあるほど、まずは「丁寧」であることがコミュニケーションにおいて「安全」であることに間違いはありません。
『みんなの日本語』の場合、19課まで「ます」「です」の丁寧体のみを扱っているのは、そういう意味もあるのかなと思っています。
M:相手や場面に合った「丁寧な」コミュニケーションができないと、あらぬ誤解を招いてしまうかもしれませんからね。
H:ときどき、カジュアルな表現だけを学びたいという学習者がいますが、日本語生成の枠組みでは活用形で丁寧かカジュアルかを表します。ですから動詞のグループ分けがわからない限りはカジュアル表現を覚えて、なおかつ使いこなすのは難しいことはお伝えすべきなのかなとは思います。
学習者の中には、カジュアル=簡単(手っ取り早く覚えられる)と思っている方もいるのかもしれないので要注意です。
教える側に思い込みはないか
M:学生さんからすると、どちらの方が負担が大きいんでしょうねぇ…
H:私の経験で言うと、学習者にとっては「辞書形」「ます形」どちらからでも活用形を覚える負担は同じだと思っています。どちらにも例外は出てきますし。
動詞が活用するもの、そしてその活用の仕方は動詞グループによって違うものという概念が入り、動詞グループの特徴をしっかり覚えることができれば、変換スピードは違えど、だれにでも(中等教育を終えていれば?)理解は可能だと思います。
どちらであっても、まずは、ます形⇔辞書形の活用をスムーズにいったり来たりできることは、大切なことだと思います。
M:ます形⇔辞書形の活用をスムーズに…。これはある程度学習が進んだ学習者でも躓くことがあるので、やはり基礎の定着のための復習は大切だと感じます。
H:活用形は学生より教える側(講師)のほうが、負担の多いものだと思います。われわれルールなんて考えず自然に覚えた言語ですから、こんな活用のルールがあったなんて!という驚きがありましたよね。
しかし、学生からは違う意見を頂戴することもありました。ロシア人の学生からは「日本語は難しくない、ロシア語のほうが難しい」と豪語されたことがあります。日本語より母語の方が複雑な活用をしていると言いたいのでしょう。スペイン人の学生からも、初級までは「平たんな道」と評されたこともあります。格変化のある言語話者からすると、さもありなんですね。
なのでこれはちょっと精神論になっちゃうのですが、講師が「日本語は難しい」「活用は大変だ」という雰囲気を出すのが、活用形を教えるときの一番のNG態度なのかなと私は思っています。
M:お話を聞いてドキっとしました。活用形の導入の時に、挫折させまいと肩の力が入っていたり、「なんとExceptionがあります!でも、もうちょっと!頑張って!」と、いかにも大変な雰囲気を出していたかもしれません。反省です。。