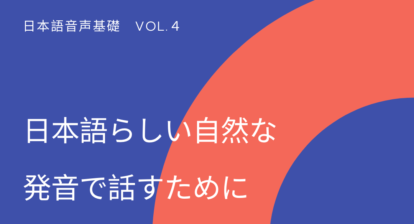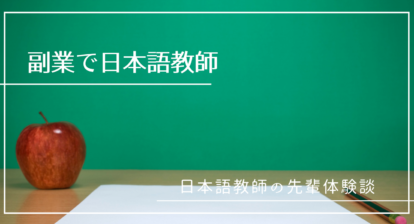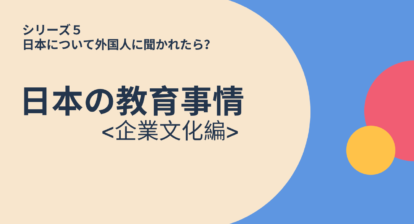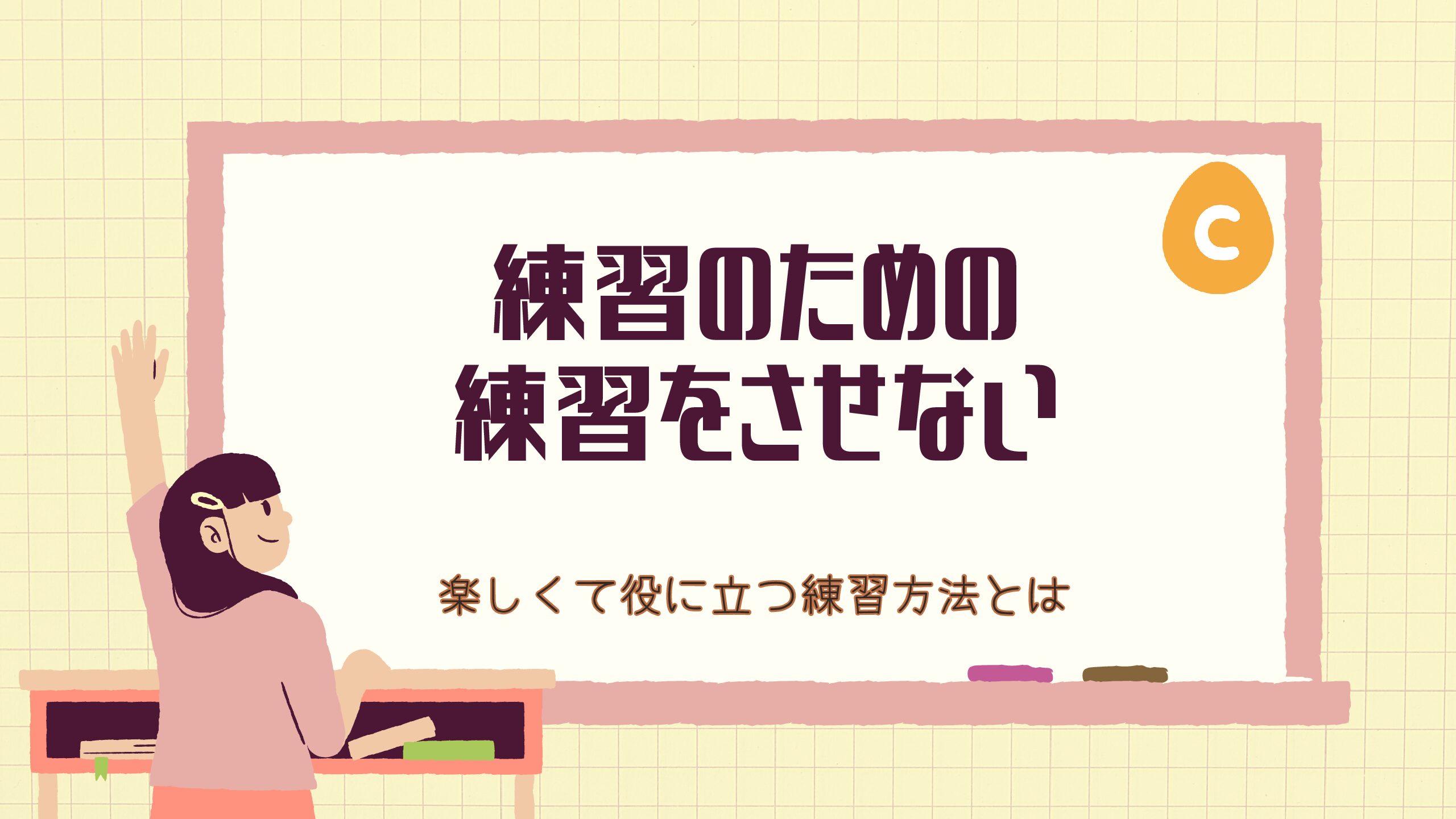「だいじょうぶです」は、どう大丈夫なのか。
店員さん:袋は?
お客さん:だいじょうぶです。
店員さん:ポイントカードは?
お客さん:だいじょうぶです。
店員さん:〇〇や〇〇のカードはお持ちじゃないですか?
お客さん:だいじょうぶです。
昨今、スーパーやドラッグストア、コンビニなどにおいては、以上のような簡略的ともいえるやりとりが日常的になされています。
この会話の中の「だいじょうぶです」は、すべての質問に対して「(袋はなくて)だいじょうぶ」「(ポイントカードや提携企業の〇〇のカードは持っていないからポイントはつけなくて)だいじょうぶ」と、提案されたサービスは要らないと「断わり」を表すために使われています。しかも、何がどうして「だいじょうぶ」なのかを説明しない、明示しないまま終わる、非常にハイコンテクストなやりとりです。もちろん、これはレジでの会計時のやりとりですから、簡潔で、ささっと流れ作業のように終わることが、お客の側にもお店の側にも求められている、必然性から生まれた簡潔表現、慣用表現だと言っていいでしょう。
しかし、これとは別に、これまで、これほどに「だいじょうぶです」が多用され、重宝されている時代があったかしら?と、感じています。そして、意味的にも機能的にも「だいじょうぶ」の適用範囲が広がってきてはいないかと思えてならないのです。
というわけで、今回は学習者も初級の段階からよく触れることのある表現「だいじょうぶ」について考えてみたいと思います。
coto講師を対象にアンケートをとってみた
まずは私の疑問を解決すべく、お店のレジでのやりとりについて、coto講師を対象にアンケートをとってみることにしました。質問は以下ふたつです。
【質問1】スーパーやドラッグストア、コンビニなどで、「袋の要不要」について質問されたとき、「要らない」場合、何と答えていますか(何と答えることが多いですか)。
回答者99人中
①だいじょうぶです。51人
②要らないです。32人
③けっこうです。9人
④その他(「その他」を選んだ方は、どんな答え方をしているか、書き込んでいただけるとうれしいです)7人
・袋、あります。
・袋、なしで。
・袋、持っているのでだいじょうぶです。
・袋、持ってます。
・(袋)あります。
・(袋)いいです。
【質問2】同じ場面・状況で、「ポイントカード」の有無について聞かれて「持っていない」場合に、何とこたえてますか(こたえることが多いですか)。
回答者82人中
①だいじょうぶです。7人
②ないですorありませんor持っていません。70人
③けっこうです。2人
④その他(実際に何とこたえているか教えていただけるとうれしいです)3人
・ないです、だけだとお作りしましょうか、と勧められるので言葉と同時に頭と手を振って少し強めに不必要をアピール。
・新しくカードを作るのを勧められないように、「ないので、いいです。」と答えています。
・ありません→(お作りしますか)→今日は結構です。あちらのマニュアルを尊重したやりとりをします。
仮説および、その検証
アンケートは以下の仮説を持って行いました。
仮説
最近「だいじょうぶです」の適用範囲がひろがっているのではないか?(とりわけ「断る」場面では、直接的な表現を避ける傾向が進んでいるのでは?)
今回アンケートの結果を通してわかったこと:仮説の検証
袋の有無を聞かれる場面では回答者のうちの半数ほど(51.5%)が「だいじょうぶです」を使っている、しかしながら直接的な返答表現である「要らないです」も3割程度(32.3%)はいらっしゃるので、「だいじょうぶ」使用者がメインストリームかというとまだそうでもないのかな?という感じです。この結果は、日本語教師界隈、しかもcoto講師の中でなので、実社会ではもっと「だいじょうぶ」の割合が高い可能性もあるのではないでしょうか(ご興味のある方は、ぜひ鋭意お近くのスーパーやコンビニでの観察を)。
一方、ポイントカードの有無についてだと、「要らないです」が全回答者(82人)中、70人(85.3%)と、8割以上を占めており、直接的な断わりの返答にためらいがない方が多いことがわかります。これは、おそらくこの文脈では、自分(消費者)の利益より、相手(スーパーやコンビニなど企業側)の利益のほうが高そうであると感じられることから、直接的な表現「ないです」で「断る」のに、心理的な負担が少ないからなのではないか?ということが考えられます。
どうして直接的表現は避けられがちなのか
実は「だいじょうぶです・いいです・けっこうです」は、丁寧度は違えども、すべて英語で直訳してもわかるとおりI am fine. That’s OK.の意味です。そしてそれを「断る」という機能に適用すれば、間接的な断わりの表現になります。言語学的には「間接的」であるということは「丁寧度」が高いと解釈されます(もちろん例外もありますが)。丁寧である(to be polite)ことは言語を用いる社会生活においてもちろん価値が高いことではありますが、もうひとつ言語使用者側の心理(直接的表現は使いにくい)という側面も注視すべきかなと思っています。
これは世代によっては断るときの「だいじょうぶです」使用に違和感を感じる人が多いこととも関係があるのかなと思っています。世代や世相により、間接表現をもちいる(直接表現を避ける)傾向が、日本語使用者には、ますます高くなっているのかなあという気はしています。
学習者にどう教えるべきか
これを受けて、学習者にはどう教えるかですが、サバイバルレベルの学習者であれば、とにかく「伝わる!」ということが何はさておき一番重要なことなので、袋の要不要についてであれば、直接的表現「~要らないです」がいいのではないかなと思っています。実際、cotoで制作したサバイバル学習者向けの教科書”Fun and Easy – 2nd Editon“では、その表現を採用しています(最初のエディションまでは「けっこうです」でした)。
サバイバル学習者の場合、聞き取りの力は大変弱いので、とにかく自分の主張だけをし、相手に理解してもらうのがコミュニケーションの第一歩であること、他の場面(レストランでデザートなどのオプションを断るなど)でも、不必要であることを伝えたいのであれば「~要らないです」という表現は利便性が高いと考えたため、この言い方を採用しています。
とはいえ、日本人は「だいじょうぶ」を使っている人が多そうなので、「だいじょうぶ」を使いたい!という学習者もいるかと思います。
なので、「だいじょうぶ」という表現が、断るときにも使えることを教えるのであれば、講師側はこの「だいじょうぶ」の意味は、「(提案されたサービスはなくて)だいじょうぶ」という意味であるということを知っておかなければなりません。というのも、文脈や場面によって「だいじょうぶ」は「はい」の意味にもなるため(実際そのような使用が多い)、どうして袋の要不要を聞かれたときに「いいえ(断る)」の意味で使えるのかという質問を受けることが多いからです。そして繰り返しにはなりますが、間接的表現のほうが丁寧度が高い、また言語使用者には断るという心理的ハードルが少ないということを心に留めておいたほうがいいでしょう。ただし、他の言語や言語社会においては、断わりも、直接的表現であることが「丁寧」であり、礼を尽くすことになることも心には留めつつ…。
時代の変化とともに
これまで扱ってきた場面(レジでのやりとり)では、学習者=購買者側という視点でしか話を展開してきませんでした。しかしながら、日本語学習者には、コンビニなどで働く労働者側になることもあり得ます。実際、coto講師向けのアンケートをとったときに、そういうご指摘を受けました(コンビニで働いている学習者が「だいじょうぶ」の意味が理解できず失敗したという例です)。お客さんの言っていること、間接表現の意味を理解できなければ、ミスコミュニケーションが生まれ、いいサービスどころか、お客さんの気分を損ねてしまう事態にもなりかねません。
「だいじょうぶ」のこのような慣用的な使いかたについては、コンビニなどの企業側のマニュアルにはない、また現場の仲間では言語学的側面からは十分な説明を受けることが難しいことも多いため、講師側がしっかりフォローしてあげられるといいですね。