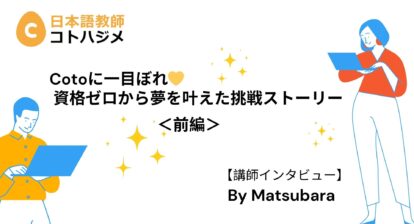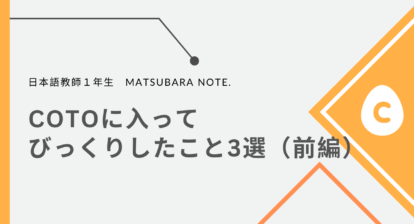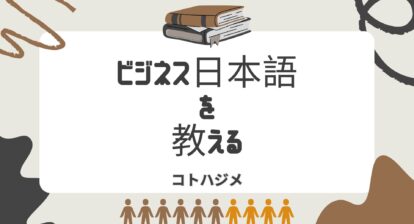モチベーションは上げるな!?
前回こちらの記事で、学習が継続できない人には共通点があるとして、モチベーションについて書きました。前編では、モチベーションとテンションの違い、モチベーションを上げることのリスク、やる気が出ない原因について述べています。
今回は後編ということで、学習ができないほどやる気が出ないときの対処法について考えています。
教師がサポートできそうなこと
①「本当にやりたいことではない」への対処法
誰にでもやりたいこととやりたくないことはあるものです。ですから、学習者のやりたい方法を一緒に探していけたら理想的だと思います。
日本や日本語にはまったく興味はないけど、仕事で必要になってしまったから仕方なく…という学習者に対しては正直言って難しいかと思いますが、ほとんどの学習者にはなんらかのポジティブな動機があるはずです。
日本の歴史が好き!マンガを原語で読みたい!職場の日本人と日本語で話して驚かせたい!議論するのが楽しい!…このような1人1人が持っている「やりたい・知りたい・できるようになりたい」のツボにハマるようなレッスンができたら最高ですよね。
私のある学生さんは、漢字の成り立ちや部首の意味などを説明すると、目をキラキラさせて面白がってくれます。そして、もっと漢字を勉強したい!と言ってくれます。このような内から自然に湧き上がってくる好奇心や、なりたい自分に近づくための行動を刺激できたら、もっとEnjoy Learning, Enjoy Lifeに近づけるのではないかと思っております。
②「取り掛かるまでに大きなエネルギーが必要な状態になっている」への対処法
ダイエット中なのに間食が止められない人がいるとします。目の前にお菓子があるのに、我慢するのは至難の業です。また、家の中にお菓子があれば、ついパクッとやってしまうでしょう。
でも、コンビニに行かなければお菓子が手に入らない状態ならどうでしょうか。出かけるために身だしなみを整え、財布やスマホをもって家を出て、お店でお菓子を選び、清算し、その後また家に戻り…と、たくさんの工程があります。「面倒だから今日はお菓子はいいや、もう寝よう」となるはずです。コンビニが遠ければなおヨシ。その行動を起こすのに、工程が多ければ多いほど取り掛かれないことになります。
すぐに取り掛かるようになるには、この逆を行います。始めるまでに手間が多ければ多いほど面倒になってしまうので、取り掛かるまでが最短になっているかをチェックします。
例えばCotoのオンライン予約システムは、毎週同じ時間にレッスン予約が自動的に入るリカーリング予約と、1回1回予約をするone-time予約があります。リカーリング予約の方がレッスン継続率が高いのは、リカーリング予約は一度予約すると、予約サイトを開く→空いている時間帯と講師を探す→予約する、という毎回の手間が省かれるからです。
上がったものは下がります。感情も躁になれば鬱にもなります。燻ぶっている火にガソリンをかけると一気に燃えますが、沈下するのも早いです。無理やり上げたものは必ず下がります。
教師がやることは、火にガソリンをかけることではなく、川の水が悠々と遠くまで滞りなく流れるようにすることだと考えます。つまり、モチベーションを上げることではなく、学習のルーティン化のお手伝いです。毎朝起きたら歯を磨く、眠気を覚ますためにコーヒーを飲む…そのようなルーティンにやる気は必要ありませんよね(それすら面倒な時がありますが)。やる気がない状態で歯を磨いても歯はちゃんとキレイになりますし、ただの習慣でコーヒーを飲んでもちゃんと眠気は覚めます。意志力をできるだけ使わないでやることが大事です。
学生が学習に取り掛かるために、そして無理なく続けていくために、障害となっていることはないか。レッスンの時間帯、学習場所、学習方法、仕事や家庭の状況などをヒアリングしたりいろいろ試したりしながら、日本語の学習が学習者の生活の一部・日常になるよう一緒に考えていきます。強いモチベーションがなくても、水が無理なく流れていくように、学習がルーティンとなるよう調整していくわけですね。
ちなみに、習慣化するためにはある程度の期間が必要だと言われています。ユーザー数125万人を誇る習慣化アプリ「みんチャレ」を展開するエーテンラボ株式会社によると、「朝、一杯の水を飲む」程度なら18日、「毎日腹筋50回」という大きな生活変化を伴うなら254日必要だということです。この定着までの期間を無事に乗り切るためにも、できるだけ取り掛かるための手間を省きたいものです。
また、同社によると「本人が継続するための工夫を3つ決める」ことも習慣化するためのコツなんだとか。この辺も教師がコーチングしながらサポートできそうですね。
③「漠然とした不安または強烈な心配事がある」への対処法
不安に思っていることや心に引っかかっていることがある時、それを思いつくまま書き出して、自分の心の中を俯瞰する方法があります。
人間の脳はワーキングメモリという機能があり、1度に3つ程度のことしか考えることができないそうです。ですから、書き出したものを俯瞰して、悩んでいることに優先順位をつけ、1つ1つ対処していきます。
これは、よほど信頼関係がある相手じゃないと一緒にできない作業ですね。基本は1人で行うものですが、時間が許せばコーチングのようにして行ってもいいかもしれません。
④心身ともに疲れている
私の学生さんに、フルタイムの仕事をしながら大学院にも通い、さらに日本語の勉強もしている大変な努力家がいます。その彼に、仕事が繁忙期で大学院でも論文に追われている時期がありました。そんないっぱいいっぱいな様子を見て、私は日本語の勉強が彼にとって人生を豊かにするどころか呪いになっていないか気になり、話を聞くことにしました。
話し合いの結果、日本語のレッスンを3か月間お休みすることになりました。また、お休み後は、スムーズに再開できるようサポートすることにしました。今、その学生さんは無事に日本語の勉強を再開し、週2回のレッスンをリフレッシュした状態で受けてくれています。時には休むことも大事ですね。
とは言え、ある日から突然レッスンを受けなくなった学生に対しては教師として打つ手がないのが現実だと思います。「あ…このままではドロップアウトしちゃうかも…」「燃え尽きちゃうかも…」と予兆が感じられた時点でアプローチをするしかなさそうです。
また、教師自身も心に余裕があることが大切だと思います。
以下の記事は日本語教師の燃え尽き症候群について書いたものです。
日本語教師が病まないために:日本語教師のメンタルヘルスを考える
こちらの記事は教師がありのままでいることの大切さをレポートしたものです。ご参考までに。
Coto全体会報告レポート① 発達障害者支援の現場から学ぶ日本語教育
「やる気が出ない」ことはダメなのか?
やる気がないことやストレスがある状態は悪いのでしょうか。いいえ、悪いとは一概に言えません。やる気が出ないというのは、心理的または環境的・身体的に何らかの問題があるというサインと捉えることができます。
また、ストレスはコンフォートゾーン(居心地はいいが成長がない現状維持の状態)から抜け出そうとすると感じるものです。ストレスをあまりネガティブに捉えなくても良いと思います。
最後におすすめの図書を2つご紹介いたします。
「スタンフォードのストレスを力に変える教科書」は、「ストレスは悪いもの」という思い込みこそが有害だとし、不安、プレッシャー、過去のつらい経験をエネルギーに変える方法が紹介されています。これを読むとストレスに対してポジティブになれます。
「習慣の力 The Power of Habit」は、人間の全行動の4割は習慣でできているとし、爆発的に売れた商品を例に出しながら習慣のメカニズムを解説しています。良い習慣をルーティン化する方法を知ることができるでしょう。