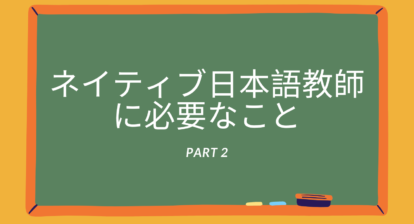Contents
「なんで分かってくれないの!」そんな時どうしてる?自分のコミュニケーションの傾向を知ろう【②解説編】
前回、日本語教師は他者を理解するために、まずは自己を知ることが大切だということで、コミュニケーションにおける自分の傾向や思考の癖に気づくためのセルフチェックをご紹介しました。
セルフチェックがまだの方は前回の記事(「なんで分かってくれないの!」そんな時どうしてる?自分のコミュニケーションの傾向を知ろう【①セルフチェック編】)からやってみてくださいね。
解説の前に、まずコミュニケーションの4つのパターンを理解しておく必要があります。
コミュニケーションの4つのパターン
①非主張的型
「非主張的型」とは、「自分の考えや気持ちを抑え、相手に言わない」コミュニケーションのパターンです。
もめ事を避けることはできるものの、根本的な解決からも遠ざかります。理解されなかったり同意したと誤解されたり、自分を押し込むことで我慢・忍耐・服従という精神的なストレスを感じやすいのも特徴です。
②攻撃的型
「攻撃的型」とは、「自分の気持ちや考えを第一に考え、相手に主張する」パターンです。
自分よりも立場の弱い人を動かすことができるという利点がある一方、勝ち負けが人間関係の中心になるため、敬遠され、孤立しやすいです。他者の従属的な態度や支えがなくては自分を維持できなくなり、相手の恨みを買います。
③作為的型
「作為的型」とは、「まわりくどい言い方や態度で、作為的に相手に結論を言わせようとする」パターンです。
相手が結論を察してくれる、自分の意見を直接伝える必要がないといったプラス面はありますが、相手に非があるように思わせるコミュニケーションのため、お互いによい気持ちがしません。
また、受動的攻撃性(ご参考:日本語婉曲表現の今昔〜回りくどい表現は「攻撃」になる??〜)に捉えられる恐れがあります。相手が期待する行動をとるとは限らず、逆手に取られてしまうことがあります。
④アサーティブ
「アサーティブ」とは、「自分と相手双方の考え・気持ちを公平に扱い、正直、素直に相手に伝える」パターンです。
相手への理解が進み、よい人間関係を築きやすくなり、ストレスが減ります。ただし、自己理解ができていることが前提であり、意識しなければなかなか身につきません。
あなたの結果は?
やっとここでセルフチェックの解説ができます(笑)
はい「〇」を数えてみてください。〇の数が10個以上なら、自分も相手も大切にするコミュニケーション(=アサーティブ)がかなりできていると言えます。
いいえ「×」がついた項目については、①非主張型の傾向がうかがえます。引っ込み思案な自己表現になっていたり、自分を大切にできていなかったりしませんか?
「〇」の横に「✓」がついた項目については、②攻撃的型か③作為的型になっている可能性があります。
結果はいかがでしたでしょうか。
それぞれのパターンに当てはめると…
さて、前回の記事で、このようなケースをご紹介しました。
参加した勉強会のグループワークの際、参加者の1人が長々と話すので、自分を含む他のメンバーが全然話せなくて、その人の独断場になってしまった。
これを上記のパターンで考えてみます。
①非主張的型の例
・苦笑いをして黙って耐える
・自分では直接言わず、誰かが言ってくれるのを待つ
・主催者に「こんな人がいたから、発言は1人〇分のように明確に指示を出してください」と後でクレームを入れるorアンケートに書く
・終わった後に周りの人に愚痴を言って鬱憤を晴らす
②攻撃的型の例
・「一人で話しすぎです」とストレートに注意する
・他の人がいる前で直接文句を言う
③作為的型の例
・時計をチラチラみる素振りをする
・わざとため息をつく
・「このワークって何分まででしたっけ?」と別の人に聞く
④アサーティブの例
・「すみませんが、あと〇分なので、先に他の人の意見を聞いてもいいですか?」と交渉する
・「時間設定が短いので、次のワークでは1人1分以内に話すようにしましょうか」と提案する
①非主張的②攻撃的③作為的のパターンは、取る言動は異なりますが、いずれも結果として人間関係に良い影響を与えません。
これらは、「なんで気づいてくれないの?」「普通わかるよね?!」「あの人オカシイ!」「こうあるべき!」といった、他責の思考と結びついていることが多いです。ですが、そもそも自分自身の思考に気づくことが難しい…
逆に、自責が強い人も「責める」の矢印の方向が違うだけで同じく問題です。一見謙虚なように見えますが、自己認識に歪みがあるという共通点があります。
長期にわたって健康的な人間関係を築くには、④アサーティブなコミュニケーションができるのが理想的です。
(なお、「アサーティブ」と「アサーション」は厳密には違う言葉ですが、大まかに言えば同じ概念で、この記事の本質には影響ないことなので、その違いについては触れません)
コミュニケーションは「スキル」
コミュニケーションスキルという言葉があるように、「スキル」なので習得することや磨いていくことができます。
今回はそのスキルを磨いていく第一歩として、自身のコミュニケーションパターンに気づくことにフォーカスしました。自分自身の傾向や癖に気づいていなければ、意識しようがないからです。
では、アサーティブであるためにはどうすればいいのか。具体的なテクニックやトレーニング方法は?…と、ご紹介したいところではあるのですが、またまた長くなってしまったので、別の機会にさせていただきます。