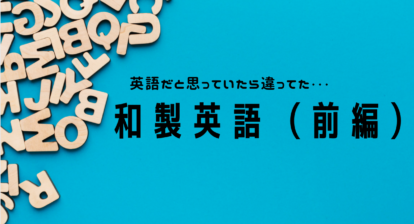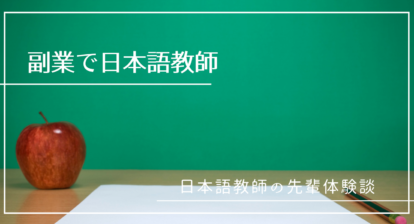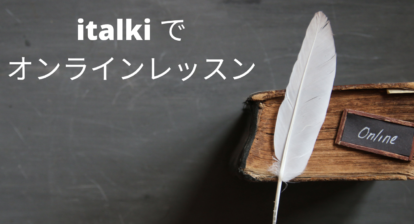モチベーションは上げるな!?
「あ…この人ドロップアウトしそう…」
私事ですが、私はとある英語学習者の集まりに参加しておりまして、ほぼ毎日勉強会やら自習会やらに参加しています。かなりの数のメンバーがいる大所帯の会で、レベルも学習目的も様々。私がその会に参加してかれこれ5年ほど経ちますが、いろいろなメンバーと接する中で、あることに気がついたのです。…学習が継続できない人には共通点がある、と。
その共通点とは、感情(やる気)の波が激しいこと。つまりモチベーションに頼って勉強しているということです。
何かのセミナーに参加したあとに燃え上がった英語への情熱を語る人、高額の教材を買ってペラペラになる!と意気込んでいる人、デキル人との英語力の差を見せつけられ負けていられない!と燃えている人…危ないです。それから数週間後…いつの間にかいなくなっています。
逆に、全然やる気があるようには見えない(失礼)のに、淡々と学習を続け、ついには海外赴任を勝ち取ったり、目標だった資格や高スコアを獲得する人もいます。
…この差は何なのでしょうか。
テンションは低くてもいい
どんな言語でも1日や2日勉強したぐらいでは身につきません。継続こそが最大のカギとなりますが、人間だもの、当然やる気満々な日もあれば、やる気ゼロな日もあります。継続という点からみると、「今日はやる気があるから朝から晩まで勉強するぞ!」「今日はやる気が出ないから勉強できない…」といったモチベーションに振り回されている状態はよろしくありません。
そもそもの話ですが、朝から晩までモチベーションが上がりっぱなしで、絶対に落ちない…そんな状態があるとしたら、躁鬱の「躁」の状態です。「モチベーション」と「テンション」を混同しているようです。テンションが低くても学習は継続できます。現に、私の学習仲間で長期間学習が続いている人は、テンションが普通~低めで、やる気があるようには見えない人(失礼)が多いと感じます。
とはいえ、学習が継続できないくらいやる気が出ないのだとしたら、何らかの問題が潜んでいるはずです。まずはその原因を考えてみましょう。
なぜやる気が出ない?
①本当にやりたいことではない
最初に一番重要な問いをします。それは、「本当にやりたいか?」です。心からやりたいと思っていることにはやる気が起こります。そして、心からやりたいと思っていないことにはやる気が起こりません。シンプルですよね。何を当たり前のことを言っているんだ!と言われそうですが、これが重要なのです。
私は日本語教師以外にも仕事をしておりまして、様々な企業で働く方々とお話をいたしますが、「実は転職を考えている」「将来のために資格をとりたいと思っている」「今後のキャリアのために勉強しなきゃ」と話してくださる方がたくさんいらっしゃいます。
そこで私が、「そのためにこれまでどんなことをしてきたか教えてくれますか?」などと質問をすると、「なかなかやる気が出なくて…」「考えてはいるんですが、特に何をやっているというわけではなくて…」「ちょっと忙しくて…」という声を本当によく聞きます。
このような状態になっているのは、具体的なやり方がわからないからではなく、本当はやりたくないからだと考えられます。「やりたい!」のではなく「やらなくちゃ…」の心理状態だから、行動が伴わないのです。そして、「重要」ではあるが「緊急」ではないので、後回しになっているわけですね。本当にやりたいことなら、疲れていても忙しくても、絶対にやるからです。
やらないことを責めているのではありません。ご本人が本当にやりたいことに気づいていなかったり、やりたくないと思っている自分を認めたくなかったりすることもあるでしょう。
「転職したら/資格をとったら/もっとお金を稼いだら、何が得られますか?」と質問してみると、しばらく考えた末に「安心…ですかね…今のままじゃ不安で」といった本心が少しずつ顔を覗かせ始めるのです。
②取り掛かるまでに大きなエネルギーが必要な状態になっている
こんなご経験はありませんか?仕事から帰宅して、ちょっとだけ休憩…とソファに座った瞬間、もう動ける体力・気力もなくなり、そのままゴロゴロしてしまう。「あ~、今朝そのままにして洗っていない食器が…洗濯物も溜まっているけど…もういいや、明日でZZZ…」と(笑)
私はこれがイヤなので、帰宅後に座らずに、やることを済ますようにしています。一度座ってしまうと、取り掛かるまで膨大なエネルギーが必要になるからです。
語学の勉強も、「よし!やるぞ!」と取り掛かるまでやる気が必要であればあるほど、挫折への道が近づいてしまいます。
③漠然とした不安または強烈な心配事がある
理性VS感情の力関係は、象使いVS象に例えられます。それは、象使いと象が押し合いをしたら間違いなく象が勝つように、理性と感情が押し合いをしたら、間違いなく感情が勝つからです。ですから、感情面でなんらかの問題を抱えている場合、「コツコツと勉強する」といった理性的な活動が妨げられてしまうのは、当然と言えます。
もし、やる気が全く起きないひどい状態に陥っているとしたら、それは無自覚に強いストレスやフラストレーション、恐怖などを抱えている場合が多いです。
そんな時に自分の心の声を聞こうとはせずに、無理やりハイテンションになる音楽をかけてみたり、根性論で頑張ろうとしたり、誰かにモチベーションを上げてもらおうとするのは、「感情のコントロール」ではなく「感情の抑圧」をしていることになります。生ごみが臭っているときに、臭いものには蓋をということで、蓋をして消臭剤を使うようなものです。
象使いがうまく象を操るためには、象の力をよく理解した上で、象が抱えている問題をじっくり観察する必要があるわけですね。
④心身ともに疲れている
先ほどの象使いVS象の例でいうと、心身ともに疲れている状態というのは、象使い(=理性)の力が弱まり、象を操るエネルギーが枯渇している状態です。たしかに疲れていてもど〜しても休めない時もありますが、この状態が続くと燃え尽きてしまいます。
では、教師としてどんなサポートができるでしょうか。長くなりましたので、次回の記事で述べたいと思います。