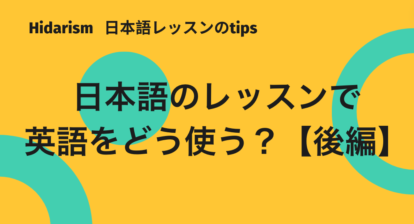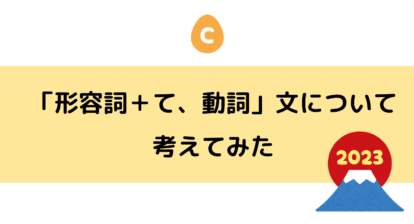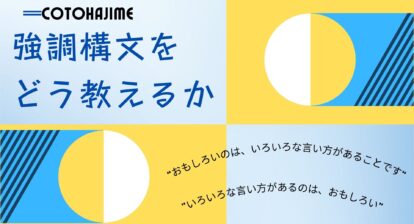Contents
日本語教師あるある!?学生の受講態度が気になるとき
これって日本語教師あるある?
いきなり私事ですが、私は日本語教師になるずっと前から、オンライン英会話レッスンを受けております。
英語レッスンを受けるときの流れは、(予習)使いたい表現や、先生に質問をしたいことをまとめておく→ (レッスン前)身だしなみを整え、先生の入室を待つ→ レッスンを受ける→(復習)とったメモを見ながら、上手く言えなかった表現を練習する。こんな感じです。
長年同じようなルーティンでやってきたので、自分としてはこれが「普通」だったのですが、先生たちに言わせると、私は「Great student!!」とのこと。私を喜ばせるためのお世辞だろうと思っていましたが、よく聞いてみると、「毎回予約はするけど、一回もレッスンに現れたことがない学生がいる」「言うことを聞いてくれず、レッスン後に泣いてしまったことがある」「メイクしながらレッスンを受けた人もいた」等云々。
…耳を疑いました。そんな失礼な態度がとれるものなのか!?同じ日本人がそんなことをしているなんて腹立たしい!情けない!…と。
そして時は流れ…、私も言語を教える立場になったわけですが…
無断欠席を繰り返す、カメラオフで参加(これはパソコンの問題もありますが)、「ながら」受講する(例:食べながら・移動しながら・料理しながら)という学生は、少ないですがたしかに一定数いらっしゃいます。
自分にとっての「普通」が相手にとっての「普通」じゃないとき、ショックや戸惑い・怒りといった感情が生まれることがあります。
プライベートレッスンならまだしも、グループレッスンともなるとクラス運営が難しくなり、頭を悩ます事態にも。
このような時、どうしていますか?
というわけで今回は、受講態度やコミュニケーションの「普通」が、自分と相手で違うときの考え方について、あれこれ述べてみたいと思います。
あっ、今回は「どうやって惹きつけるレッスンをするか」といった教授論や、「健全なクラス運営のためには」といった組織論ではないので悪しからず…。
現実的な解決ができるか
「いつもタクシーの中からレッスンを受けるから、落ち着かない」「宿題をしないとついてこれないのに、してこない」など、自分にとっての「普通」が相手にとっての「普通」じゃないことは、よくあります。日本人同士でもあるのに、文化的背景が様々な学生を相手にするのですから尚更です。
さらに教師なんて職業の人は、もともと勉強好きで、その上、人のために一生懸命になれる人が多いでしょうから、「相手が理解できない…」という状況には出会いやすいでしょう。
まず、大前提として、現実的に解決できるものであればした方がいいですよね。
① お互いに快適にレッスンを受けられる仕組みがあるか
対面の学校でもオンラインでも、快適にレッスンが実施できるよう、適切なレッスン環境の奨励や禁止事項を、誰にでもわかる形で明示しているのかが重要だと思います。
その上で、学生がそれに従わないのでしたら、それは学生サイドの問題です。もちろん教師側にも自己検証は必要でしょうが、こちらに非がない場合は、思い悩む必要はないでしょう。
② 日本語ネイティブがどう感じるか
私たちは日本語教師である前に、いち日本語ネイティブです。一般的な日本人がもつ感覚は大事にするべきでしょう。
学生が学ぶ言語が日本語であるということは、コミュニケーションをとる相手は当然日本人のはずです。
学習者に悪気がなくても、一般的に日本人が不快と感じるであろう態度や所作に関しては、その旨を伝えていいと思います。
日本語ネイティブとしてどう感じるのかを、ありのままに伝える。これは巷の日本人には期待できず、教師という立場だからこそできることではないでしょうか。
その際、経験談を交えてもいいかもしれませんね。例えば、コロナ禍で一瞬流行ったように見えたオンライン飲み会。私含め、アレが苦手だったという日本人はかなりいるようで、ネガティブな感想をけっこう耳にしました。
オンライン飲み会が浸透しなかった理由は、自粛が終わった以外に、「マナー的に良くない」「品がないように見える」「なんだか相手に申し訳ない」「気を遣ってしまう」といった心理的な抵抗が強いからのようです。つまり、コミュニケーションスタイルが、多くの人に合わなかったのでしょう。
③ 交渉できるか
戸惑いや不満を我慢してため込むのではなく、上手に伝えて交渉してみる。一番いいのはやっぱりコレです。
例えば、毎回「ながら」受講している学生さんには、「このレッスンはたくさん発音練習があるから」「共有画面でじっくり文法を説明したいから」などの理由を伝えて、「こうすることはできるか」「こうしてくれたら助かる」と正直に、率直に、誠実に伝えます。
これは、対等で健康的な関係を長期的に築いていくためのアサーティブ・コミュニケーションという手法の基本です。
「普通は言わなくても分かるよね」と相手に察してもらおうとしたり、「ながら受講するのは、きっと忙しい中、時間をこじ開けて受けてくれているからだろう…」と決めつけ、相手に自分の意思を伝えないのは、かえって不誠実となります。
時間をかけて準備したのに!
ここからは、マインドセットについてのお話になります。
「日本語教師という仕事は感情労働だ」と、私はこのコトハジメに幾度となく書いてきました。感情労働は、直接的にやりがいを感じやすいですが、精神的に疲れやすいという側面もあります。
どんな時に精神的な疲れを感じるのか。例えば、「のに!」が口から出てきたとき。
「時間をかけて準備したのに!」「こっちが一生懸命説明しているのに!」と、一度は思ったことがあるのではないでしょうか?
この「のに!」は、「べき思考」と結びついています。
べき思考は、「休むなら、せめて一報入れるべき。なのに…」「相手に失礼のないように、レッスンは落ち着いた環境で受けるべき。なのに…」などの心の声となります。
また、べき思考は、被害者意識や他責にも繋がりやすいです。私自身、この「べき思考」が非常に強く、自分にも他者にも厳しい人間でした。厄介なことに、自他ともに厳しい人は、自分が厳しくなっていることに気づくこと自体が難しい…。
まずは、自分自身が「べき思考」に雁字搦めになっていないか、ゆっくりお茶でも飲みながら振り返ってみるのもいいかもしれませんね。
その際は、こちらの記事(日本語教師が病まないために:日本語教師のメンタルヘルスを考える)も参考になさってみてください。
他者の問題を自分の問題としない
次に、何か問題があったときに、必要以上に悩まないために大切な考え方について触れます。それは、心の境界線を引くことです。「他者の問題」は「自分の問題」ではありません。
心の境界線についても、こちらの記事(日本語教師が病まないために:日本語教師のメンタルヘルスを考える)で触れました。
他者と自分の境界線があいまいな状態は、相手を自分の思い通りにしようとしたり、「やってくれない!」と他責に陥ってしまったり、逆に相手に巻き込まれてしまったりする危険性を孕んでいます。
心の境界線を引くとは、つまり、教師としてやるべきことはやる、言うべきことは言う。でも、教師の言う通りにするかは学生の選択に任せる(=自己責任)、という考え方となります。
特にCotoは、教師と学生が対等な関係ですので、このように境界線を引くのは、一人の人間として相手を尊重する意味でも大切な考え方だと感じております。
期待しないから感謝できる?!
最後にもう少しだけ。そもそものお話ですが、ここまで触れてきた「のに!」「べき!」から生まれるショックや戸惑い・怒りといった感情は、相手に期待しているからこそ生まれる感情なのではないでしょうか。もちろん、みなさん一生懸命仕事をしているんですから、生まれて当然の感情ではあります。
ただ、その期待が高くなりすぎていないか、注意が必要だと思います。
対象(学生や職場)に何も期待してない状態を「ゼロ」とすれば、「1」でもプラスになれば対象に対して感謝が生まれます。レッスンに出てくれてありがとう!(感謝)、集中して受講してくれてありがとう!(感動)、サポートしてくれてありがとう!(感激)となります。
私は、自分が傷ついたり、がっかりしたり、誰かを恨むのが嫌で、(これはたぶん悪いことなのですが)対象に「何も期待しない」という変な思考の癖がついてしまいました。私はこれを勝手に「期待ゼロ理論」と名付けています。
それはCotoに入った時も同じで(ご参照:「日本語教師1年生による「cotoに入ってビックリしたこと3選」)、会社に1ミリも期待していなかった分、「こんなにやってくれるの!?」と感激の嵐でした。
また、最近こんなこともありました。レッスン中に、スマホを見る癖がある学生がいます。それでいてレッスンに消極的というわけでもなく、これといった支障もなかったので、私は気にもせず、そして何も期待していませんでした。
あるとき、その学生が「これを見てください!」と、私にLINEのメッセージ画面を見せてくれました。
実はその学生、レッスン中に習った表現を使って、その場で日本人の友人にメッセージを送っていたのです。そして、画面を見せてくれたのは、私が「日本人ならきっとこういう反応をするはず」と言った通りの反応を、メッセージの相手がしたからなのでした。
その学生は、私の「レッスンで習った表現は、すぐに日常で使ってみてネ!」というアドバイスを忠実に実行していたのです。
「期待ゼロ」から「感激100」になった瞬間でした。