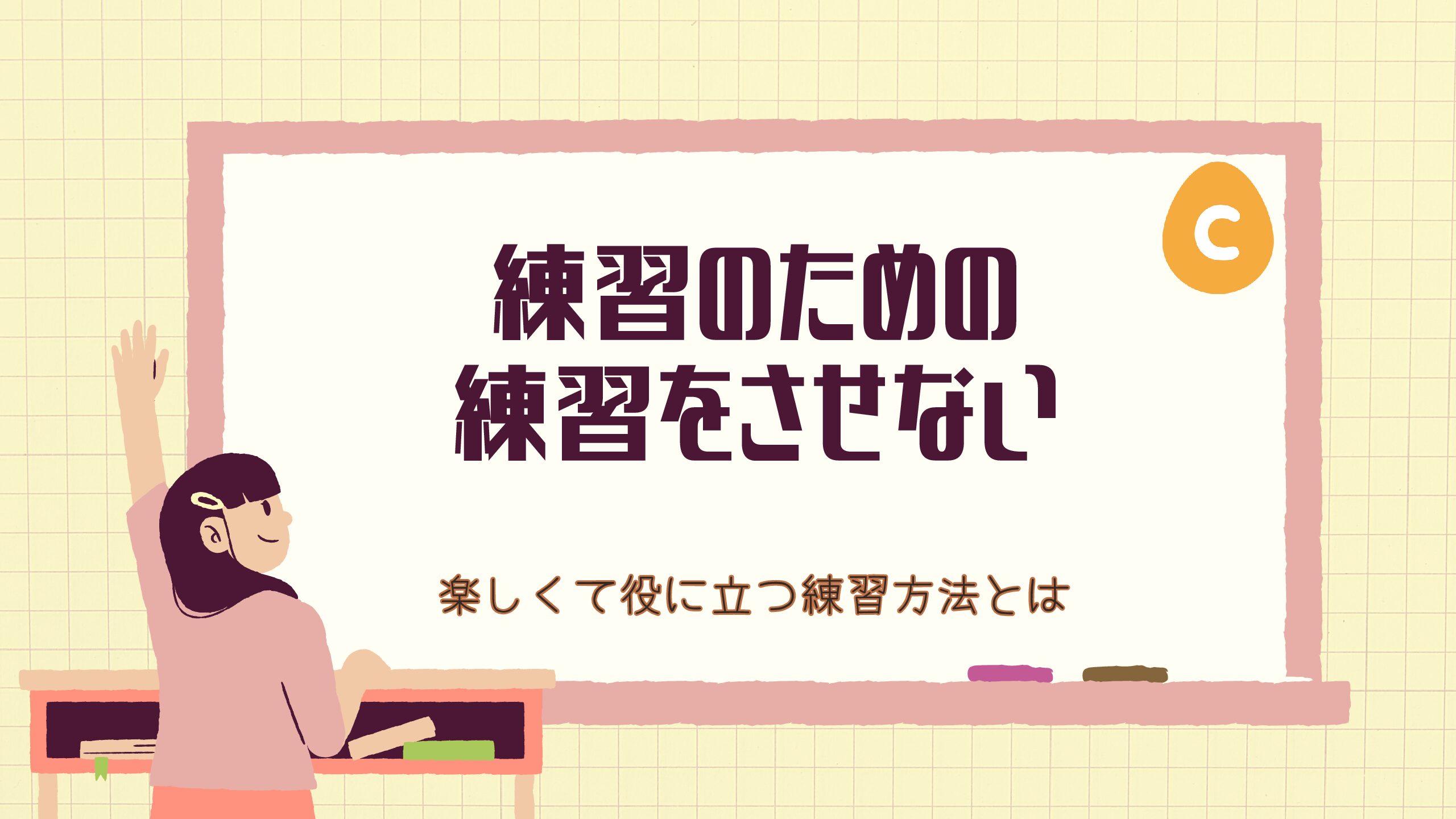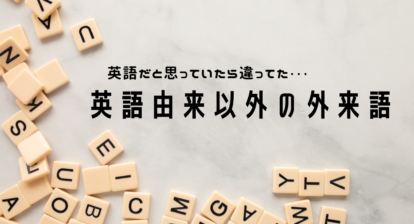Contents
【どっちでもいい…は危険?】フレキシブルな日本語の語順 初級学習者にどう教える?
日本語は語順がフレキシブル
突然ですが、学生から以下のような質問があったとしたら、どのように答えるでしょうか?
①「京都で写真をたくさん撮りました。」
②「京都でたくさん写真を撮りました。」
この2つの文は同じですか?どっちがいいですか?
うーん…「どっちでもいいよ」と言いたくなっちゃうなぁ…。
では、こちらはどうでしょうか。
①「猫が何かもってきました。」
②「何か猫がもってきました。」
この2つの文は同じですか?どっちがいいですか?
②「何か猫がもってきました」でも意味は通じますが、①「猫が何かもってきました」の方が自然な気がします。「どっちでもいいよ」と答えるのは、なんだか抵抗があります。
例えば「配置の言語」とも言われる英語は、語順が変わると意味が変わったり文法上間違いになったりすることも多々ありますが、対して日本語は語順がフレキシブルです。助詞さえ間違っていなければ、意味が通じることが多いです。
では、意味さえ通じれば日本語の語順は自由!と教えていいのでしょうか。もう少し見てみましょう。
『GENKI』で語順を見てみる
Cotoでもよく使用される『GENKI』(第4課)に記載の文を例に、語順を見ていきたいと思います。
①私はきのう京都に行きました。
(誰が→いつ→何をした)
②けんさんはうちで本を読みました。
(誰が→どこで→何をした)
③メアリーさんはソラさんと韓国に行きました。
(誰が→だれと→何をした)
このように「誰が→いつ→どこで→だれと→何をします/した」の基本的な語順があることがわかります。
ためしに、以下のように語順を入れ替えてみます。
①きのう京都に私は行きました。
②うちで本をけんさんは読みました。
③韓国にメアリーさんはソラさんと行きました。
助詞が正しければ意味は通りますが、ちょっと違和感がありますよね。
では、冒頭に出てきた「たくさん」のような副詞の位置についてはどうでしょうか。『GENKI』にはこのような記述があります。
京都で写真をたくさん撮りました。
京都でたくさん写真を撮りました。
野菜がたくさんあります。
たくさん野菜があります。
Expressions of quantity in Japanese are rather different from those in English. In Japanese, if you want to add a quantity word like たくさん to the direct object of a sentence, you can either place it before the noun or after the particle を.
(日本語における量の表現は英語とはかなり異なります。日本語では、「たくさん」のような量の語を文の目的語に付け加えたい場合、名詞の前に置くか、助詞「を」の後に置くことができます。)
ということで、一定のルールがあることがわかります。
我々日本語ネイティブは、実生活では語順を自由に変えています。そのため、学生にも「語順を変えても意味がわかるから、どっちでもいいよ」と言いたくなります。
ただ、特に学生が初級のうちは、「誰が→いつ→どこで→だれと→何をします/した、の順」や「副詞は名詞の前か、助詞“を”の後に置く」と、固定化した語順を意識して教えた方が、メリットが多いように思います。
固定した語順で教えるメリット
なぜ語順を固定して教えた方がいいのでしょうか。その理由をまとめてみます。
1)疑問文が作りやすくなる
「何時に」「誰と」「どこで」など、日本語の疑問文は助詞とくっついていることがほとんどです。疑問文が作れないのは、平叙文での語順とそれに付随する助詞のコントロールができていない可能性があります。このコントロールのためには、語順を固定化して練習するのが近道となりそうです。
2)型に入れたほうが長い文章を作りやすい
外国語の勉強に限らず、なんでもいいよ!どっちでもいいよ!と言われると、かえって動きがとれなくなることはありませんか?
まずは「誰が→いつ→どこで→だれと→何をします/した」と型に入れる方が、混乱せずに、長い文を作りやすくなると考えられます。
3)教師への不信感を防ぐ
ちょっとおまけ的な話になりますが、語順がバラバラだと、「先日と違うこと言っているなぁ」「あの先生はこう言っていたのに…」と、先生への不信感を抱かせてしまうかもしれません。これを防ぐためにも、基本の語順を意識する方が、リスクヘッジになるように思います。
教える時の注意点
ここからは、レッスンでの注意点についてお話します。
1)説明しすぎない
「なぜこのような語順なのかというと…」「日本語はフレキシブルだから実際には…」といったことは、初級のうちはあえて説明しなくてもいいと思います。良かれと思っていろいろと説明することで、学生がかえって混乱してしまうかもしれないからです。
語順を意識しだすのは、『GENKI』では、「を格」「で格」「に格」「へ格」が登場する第3課あたりです。やっと平仮名・カタカナが読めるようになってきた段階のはずですので、説明しすぎに注意しましょう。
2)視覚的サポートをする
言葉だけでわからせようとするよりも、イラストや穴埋めなど、視覚的に理解できるものがあるとよいと思います。クイズのように楽しんでできたらいいですね。
3)たくさんパターン・プラクティスをする
パターン・プラクティスはどの文型でも行っていると思いますが、以下のような拡張練習をして、どんどんセンテンスを長くしていくと、Step by Stepで無理なく「長い文が作れた!」「言いたいことが言えた!」という達成感を味わうことができるでしょう。
例
T:コーヒー→S:コーヒーを飲みます。
T:カフェ→S:カフェでコーヒーを飲みます。
T:友達→S:友達とカフェでコーヒーを飲みます。
T:3時→S:3時に友達とカフェでコーヒーを飲みます。
他に変換練習や代入練習などもよさそうですね。
4)疑問文を作る
疑問文を作ってもらうことで、学生の定着度を確認できます。
例
きのう渋谷で友達と会いました。
→いつ友達と会いましたか。
→どこで友達と会いましたか。
→だれと会いましたか。
日本語の語順は確かにフレキシブルですが、「自由=何でもいい」ではありません。特に初級学習者にとっては、まず「型」を手がかりにしながら文を組み立てていくことが、自信と正確さにつながると考えます。
基本の語順を示し、視覚的なサポートや様々な練習を通して、少しずつ文を伸ばしていく。その積み重ねが、やがて語順のゆるやかな変化も自然に使いこなせる力へとつながっていくでしょう。
「語順はフレキシブル」という日本語の特性は、むしろ学習者にとって大きな味方とも言えそうです。まずは基本の型をしっかり身につけてもらい、その「土台」の上で自由さを楽しめるよう、段階的に導いていきたいですね。